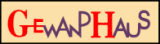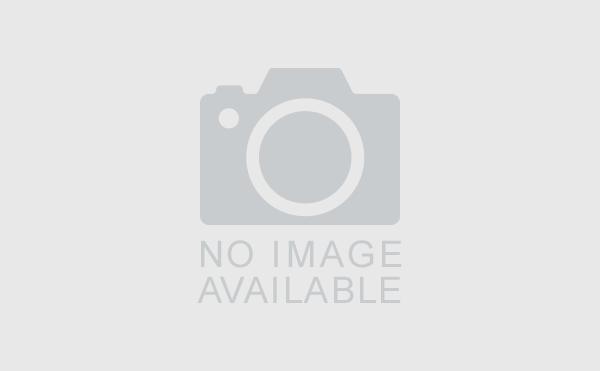ベートーヴェン交響曲第四番変ロ長調Op.60
あと千回のクラシック音楽リスニング(37)
ベートーヴェン交響曲第四番変ロ長調Op.60
〜 カルロス・クライバーの鼻から高速指揮への妄想 〜
カルロス・クライバー指揮バイエルン国立管弦楽団
Orfeo S100841B(LP)
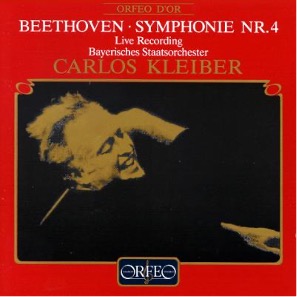
ベートーヴェンの交響曲第四番、「あと一歩の名曲」の代表である。
ベートヴェンが生きていたら、「わしのこの交響曲をこんなジャンルに入れるのか」と激怒するに違いない。ごもっとも、である。何せ、かの「傑作の森」の中の一作なのだから。
名曲の資格十分、いや十二分である。それどころか、全交響曲9曲のうち、私の周辺にはこの曲が一番好きだと断言される方も少なからずいる。
私にとっても、随分と前から一番取り出すことが多いべートーヴェンのこの交響曲となっている。特に第一楽章の「不安」の序奏から主題に飛び込むスリル、フィナーレの生命力そのもの、溢れるエネルギーの奔流。素晴らしい。
しかし、この交響曲は人類全体を震撼させるようなベートーヴェンの強烈なオーラには不足しているかもしれない。
標題がない、秀峰「エロイカ」と「運命」の谷間に位置する作品ということで、第八と初期の第一及び第二とともに超傑作とは言い難い作品、よって堂々と「名曲」というジャンルになかなか入ってこないのではないか。しかしである、これはもしかすると超傑作なのかもしれない。シューマンの第三と第五に挟まれた「ギリシャの乙女」、そんな作品評はありえないと断言できるほど男性的な力に溢れた作品である。長調よりも短調という私でも素晴らしい魅力を感じる。
変ロ長調という調性の選択、私はこの調性は「官能性」に結びついていると勝手に確信している。この漲る幸福感、これは酒呑みが美酒と出逢い、その旨さに酔うというような幸福感とは別物である。いやはや、この作品の持つ、溢れ出るようなエネルギーには恐れ入る。この幸福感、溢れるエネルギー、ベートーヴェンは舞い上がっているのだ。
その官能的な面がさらに濃厚に表出されているのが作品番号で1番違いのヴァイオリン協奏曲ではないのか。ドアをノックするようなティンパニで始まり、いかにも立派な構えの序奏に続いて現れる、なよなよとした艶麗そのもののようなヴァイオリンのソロ。べ―トーヴェンらしく構成感がしっかりとした作品(いや、初演日に間に合わせるため練りが足りないと言う印象もある)であるにもかかわらず、艶っぽさ満載の趣き、こんなお色気たっぷりのベートーヴェンは珍しい。
これら二つの作品から自明なのは「ベートーヴェンは恋をしていた」という事実であろう。
なので、英雄を崇めるとか、「運命はかく扉を叩く」というような大きなテーマではなく、個人的な感情表出みたいな趣が滲み出ているのだと考えられる。テレーゼとの恋のなせるわざであるに違いない。
さて演奏に移るとこの作品の持つエネルギーを最大限に抽き出しているのはカルロス・クライバーであろう。この演奏はクライバー自身、「何人の批評も受け入れない」と語った自信作である。
で、あるのだが、さる方が呟いた。「クライバーは好きではない。交響曲ではテンポが速くて、味わういとまがない」と。電光石火のような演奏、確かにそうかもしれない。しかし、ムラヴィンスキー&レニングラード・フィルにしても、これまたテンポが速い。私は娘の家族が飼っている「クララ」という名のゴールデンレトリバーを思い浮かべる。ある時期ミカンが大好きで、あっという間に呑み込んでしまう。そして、次をねだる。ミカン好きの犬なんて気味が悪いが、娘に問うてみた、「あんなに速く呑み込んで、味が分かるのかねえ」と。「分かるみたいよ、嫌いなものはけっして呑み込まないから」というのが答えであった。
ところで、私はある時までクライバーにユダヤの血が入っているなんて想像もしなかった。ところが、彼のポートレートを眺めていると、彼の鼻が気になり始めた。所謂、「鈎鼻」である。それで、調べてみると母親がユダヤ系アメリカ人であることが分かった。アルゼンチンの米国大使館で勤務している頃、エーリッヒ・クライバーと出逢ったようだ。最初、お互い母国語でのコミニュニケーションが出来ないカップルだったらしい。でも結ばれた。これまた奇蹟に近い。
私は会社の研究顧問をやっている折、国際会議出席のため、一度だけイスラエルを訪れた。1週間ほどの滞在であったが、このユダヤの国でいろんな体験をした。乗り合いバスで空いている席に座ったら、隣の青年兵士が小銃を抱えていた。「嘆きの壁」では異様な祈りの場面に接した。死海では水浴びもやった。音楽でもシナゴーグではなく教会でペルゴレージ「スターバト・マーテル」を聴いた。これまでで最高のカバブ―を食したのもこの国であった。
その折、同じ植物病原細菌の研究をやっているヘブライ大学の教授と面会する機会があったが、その教授の耳はまるで宇宙人のそれ、「鉤鼻」やそういう形態学的特徴はさておいて、私はユダヤ系アルゼンチン人音楽家の感性には深い興味を持つ。彼らの多くはナチ時代にヨーロッパから南米に移民してきたユダヤ人のカテゴリーに入るであろう。あるいは、戦後は逆に戦争裁判を逃れてきたナチ残党とかその類のドイツ人。
アルゼンチンは南米の国で文化の程度が高い国である。ブエノスアイレスは美しい街である。ブエノスアイレスにはフルトヴェングラーも度々訪れたコロンヌ劇場(テアトロ・コロン)まである。このテアトロ・コロンでエーリッヒ・クライバーは10年間主席指揮者を勤めた。私も一晩だけこのオペラ・ハウスを訪れる機会があった。プログラムは残念ながらバレエ「ロメオとジュリエット」(プロコフィエフ)でオペラではなかったが、エーリッヒ・クライバーを偲ぶことができた。まあ、一期一会の世界である。
さて、上述したように、音楽関係者にはユダヤ系が多かったので、そういう文化的土台の上にダニエル・バレンボエム、ミヒャエル・ギーレンなど著名な音楽家を輩出しているのである。
その中で、カルロス・クライバーとマルタ・アルゲリッチに沢山の共通点を見出す、この二人には、花火的な美学が確かに存在するような気がしている。カルロスはアンコールで「こうもり」序曲と同時に、ヨハン・シュトラウスⅡの「雷鳴と電光」を必ず取り上げる。このアンコール曲がカルロスの特質を集約していると考える。
私はベートーヴェンの第四交響曲ではクライバーのテンポもありかなと肯定的な考えを持っている。そして、時にそのエネルギーの迸りに快感のようなものを感じる。ここに挙げたバイエルン国立管を振ったディスク(まだLPの時代だった)以外にもクライバーなので海賊晩も多い。ただ、この作品でのバイエルン国立管はクライバーの信頼は厚いものの、ドイツ的なださい(というか柔軟性のない)響きが気になる。リハーサルでクライバーが説く、「マリー、マリー」ではなく「テレーゼ、テレーゼ」というニュアンスがウィーン・フィルのメンバーは理解できず、業を煮やしたクラバーはキャンセルしてしまった。返す返すも残念、このコンビでの演奏を聴きたかった。クライバーの高速指揮を受け止めて、その拍より僅かに遅れて、エレガントさが加わると予想される演奏、それが聴けないのが悔やまれる。
クライバーには幸運なことに名門アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団とのライブの映像盤が残されている。いい映像である。私はかって、これとクラウディオ・アバドのエディンバラ音楽祭でのヴェルディ「レクイエム」の2枚によって、LDプレーヤー購入を決めた。高速指揮は相変わらずでフィナーレでは老ファゴット奏者が気の毒になるほどのテンポであるが、ほれぼれするような指揮姿である。
クライバーの高速指揮は素晴らしいが、その一方で、ブルーノ・ワルター、ハンス・シュミット=イッセルシュテット、アンドレ・クリュイタンスといった優雅な演奏も好きである。とくに後二者はウイーン・フィルとベルリン・フィルという最高のオーケストラを振っての録音である。
クリュイタンスは私の贔屓の指揮者であった。私が大学生の頃、音楽好きの連中が集まっては、現在誰が最高の指揮者かという議論をよくやっていた。カール・ベームか、ヘルベルト・フォン・カラヤンか、それともアンドレ・クリュイタンスか、情報が限られているだけに皆思い込みでの議論であった。
クリュイタンスはベルギー人、ラテンとゲルマンのはざまの国なので、バランス感覚が凄い。調和型の人間性、まるでカルロスとは好対照である。そして、何とベルリン・フィルで最初にベートーヴェンの交響曲全集を録音した指揮者なのである。私はこの中で特に第六番「田園」に魅かれていた。そのことは拙著「クラシック33名盤へのオマージュ」で詳しく述べた。
第四番についても全く同じことが言える。端正でセンス抜群なのである。しかも、ベルリン・フィルはフルトヴェングラーが亡くなって、まだ3年しか経っていないというタイミングなので、SACDでは全体にわたって重厚、低弦の鳴りが素晴らしい。
クリュイタンスはベルギー人として初めてバイロイト音楽祭に招かれ、前途洋々であったのだが、眼の癌に侵され、これからという時に亡くなった。グルメでコニャックを愛したクリュイタンス、あと少し長生きしていたら、シャルル・ミュンシュではなく彼がパリ管を得ていたであろうに。
当時バイロイトでは歌姫アニア・シリアが登場し、大評判となっていた。そして、彼女はヴィーラント・ワーグナーとの道ならぬ恋に陥ったのである。しかし、ヴィーラントは1966年に病で急逝する。何と49歳であった。
そのアニア・シリアの次のお相手がクリュイタンスであった。上述したようにクリュイタンスも宿痾の病に倒れてしまい、彼女の運命は痛ましい。しかし、その後、彼女はクリストフ・フォン・ドホナーニと結ばれる。まさに「運命の女」とも言えそうである。
演奏に戻って、別格のフルトヴェングラーも凄い。特に戦時中の録音は凄演そのもの、鬼神が乗り移ったかのような演奏である。戦後のウィーン・フィルとの落ち着いた演奏も素晴らしい。丁度、「エロイカ」でのウラニア盤とEMI盤との演奏の差そのものである。
再び、クライバーの話に戻ると、彼はベルリンに生まれ、多感な時期にチリで親と離れて暮らし、その後、ようやくブエノスアイレスで家族と一緒の生活が始まった。このように、本物の母国を持たない、さまよえる生き方、これこそがユダヤ的なのである。
カルロスは9歳で作曲を始めるなど楽才を示したが、父エーリッヒはカルロスに音楽の道に進むことを許さず、カルロスはチューリッヒ工科大学で化学を学ぶようになる。ところが、音楽への夢断ちがたく、20歳の時にブエノスアイレスで1年間だけ音楽を学ぶことを許される。それまでスコアを読むことさえ禁じられていたという。カール・ケラーという芸名でデビューし、チューリッヒ、デュッセルドルフ、シュトットガルトで修業し、ミュンヘンでスターとなった。チューリッヒ時代には「白鳥の湖」まで振らされたらしい。
エーリッヒ・クライバーはアルゼンチン移住の前は10年ほど、ベルリンでフルトヴェングラーとライバルの関係にあった。長身痩躯で哲学者的風貌のフルトヴェングラーに背丈で劣っていたエーリッヒは「もう少し背が高かったら、私の人気も上がるだろうに」と嘆いていたそうである。息子カルロスはほぼハイブリッド、遺伝的に父親の音楽的才能と母親のフィジカルな優雅さを受け継いでいた。
しかし、天才的カルロスは徐々に理想を追い求め、現実と妥協しなくなる。クライバーのレパートリーの狭さ。カラヤンの後継者として名前が挙がった時、彼自身は「ありえない、こんないくつかの作品しかレパートリーのない私が」と自虐的な言葉を吐いたそうである。しかし、クライバーはブルックナーにしろ、マーラーにしろ、どの作品も隅々まで口ずさむことができたそうである。スカラ座での「オテロ」で主役のプラシド・ドミンゴのミラノ入りが遅れた折、リハーサルでドミンゴの歌唱の部分はクライバーがすべてを唄ったらしい。周囲は感動したそうな。やはり、天才なのである。大統領の要請があって、ベルリン・フィルでブラームスの第二をメインとするコンサートを振ったが、その前にも「新世界より」を振る予定があったそうである。どんな演奏になっていたのか、キャンセルがまことに残念である。
クライバーのベートーヴェンは凡庸なドイツの指揮者の構成を重んじた定型的な指揮ではなく、流動体とも称すべき、そして火を噴くような熱いパッションが特徴の指揮なのである。
セルジュ・チェリビダッケをして「何であんなに恐ろしく速いテンポで指揮するのかね。あれでは音楽の神聖さは抜け落ちてしまう。悲劇的だね」と言われようとも、なのである。
最後に、「クライバーの鼻」と書いてしまったが、巷では長い間、カルロスはアルバン・ベルクの息子だと言う無責任な噂が流れていたという。その一つの根拠は鼻が驚くほど似ている、ということであったらしい。しかし、その骨相上の類似については結論が出なかったそうである。
その根拠としてクライバーは1948年に鼻を手術、1966年には自動車事故での鼻の変形が加ったが、それ以前はアルバン・ベルクと全く似ていなかったとのこと。しかし、意味深な噂である。
アルバン・ベルクの傑作「ヴォツェック」(私はブタベストからの帰途、ウィーン国立歌劇場でアバド指揮の公演に接し、感動した)の初演者がエーリッヒ・クライバーで、それは137回にも及ぶリハーサルを経ての公演であったという。カルロスも後年は振らなかったが、シュトットガルト時代には重要なレパ-トリーで、エディンバラ音楽祭でも引っ越し公演を振ったが、2日目にキャンセル事件を引き起こし、大スキャンダルとなった。
まあ、そういうものであろう、天才なのだから。このカルロス指揮のベートーヴェン第四交響曲でそれを確認しながら清聴することにしよう。