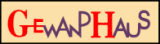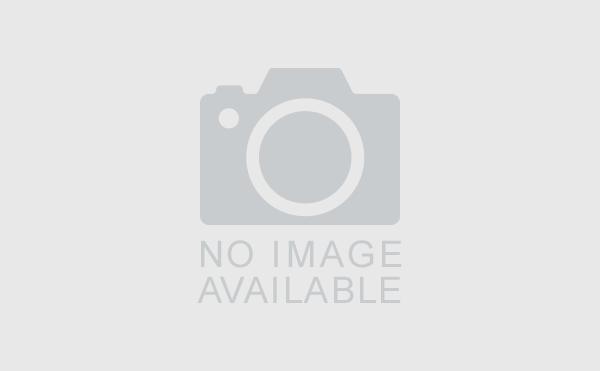マーラー:「大地の歌」
あと千回のクラシック音盤リスニング(43)
マーラー:「大地の歌」
〜 ジンクスを破れなかったマーラーの晩年の傑作に耳を傾ける 〜
ミルドレッド・ミラー(MS) 、エルンスト・ヘフリガー(T)
ブルーノ・ワルター指揮ニューヨーク・フィルハーモニー交響楽団
CD: Sony Classical SMK 64455(輸入盤)
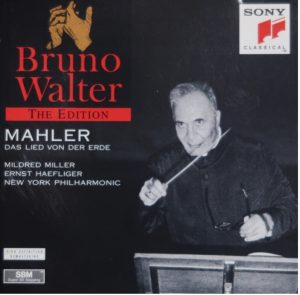
この「大地の歌」は交響曲として扱うのか、歌曲集として扱うのか、前者が優勢ではあるものの後者も「可」という難しい作品である。ロリン・マゼールなどオーケストラ付きの巨大な声楽作品と言ってはばからない。従って、彼がウイーン・フィルハーモニーを振ったマーラー交響曲全集にはこの「大地の歌」は含まれていない。
それもこれも、マーラーは“第九のジンクス”を恐れていたためである。マーラーは尊敬していたベートーヴェンやブルックナー等偉大な作曲家の交響曲の最後が「第九」であったため、「第九」というナンバーリングを避けた。しかし結局、10番目の交響曲を完成させることは出来なかったので、やはり「第九」が最後の完成交響曲となった。
この「大地の歌」はブルーノ・ワルターにとって最も大事な作品、何せ第九と同様、ワルターはこの作品の初演行った指揮者なのである。
なので、作曲者マーラーの意図やアナリーゼを知った指揮者ということになる。弟子筋のもう一人の指揮者がオットー・クレンペラーである。ワルターとクレンペラー、二人の対照的な芸風や取り上げるマーラーの作品の嗜好を比較するのは非常に面白い。因みに、この「大地の歌」は双方が複数回録音したレパートリーである。
1960年のマーラー生誕百年祭、ワルターはウィーン芸術週間でマーラー交響曲第四番を振った。前プロがシューベルト「未完成」で、神々しさが漂う演奏と評された。私は音の悪さを覚悟して、このコンサートのライブ盤LPを手に入れた。予想通りの音で、ORFの怠慢に腹が立った。時は1960年なのである、ステレオ録音どころか、何故映像を録らなかったのだろうかと考えてしまう。
それはともかく、第四交響曲は最もワルターに向いた曲で、実際戦後もよく取り上げた作品ではあった。当然、ワルターが自ら選んだプログラムと私は思い込んでいた。ところが、ワルターはこの「大地の歌」を振りたかったらしいのである。しかし、音楽祭の事務局は「大地の歌」はすでにカラヤンが振ることになっていたので、カラヤンに気兼ねして希望は聞き入れられなかった。実現していればどういう演奏になっていただろうか。円熟の「大地の歌」か、それを通り越して枯淡の「大地の歌」となっていただろうか。それはともかく冒頭のホルンの咆哮や、同じ楽章の中間部、秋風が吹きこむような弦の音、ウィーン・フィルによる「大地の歌」をDECCAのステレオ録音でぜひとも聴いてみたかった。
そして、今回採り上げたワルター指揮ニューヨーク・フィルによる「大地の歌」の録音は1960 年4月18日及び25日にニューヨークのマンハッタン・センターで行われた。つまり、ウィーンに出向く少し前に、ということになる。この年、ワルターはもう84才になるという高齢、しかも、心臓の問題を抱えていたにもかかわらず、4月から5月にかけてビバリーヒルズからニューヨークへ、それからウィーンという行程で移動した。この二つの主要都市でのマーラー生誕百年祭のイベントでの指揮には敬意を表したい。老ワルターの執念と言ってもよいであろう。
因みに、この年の初頭から春にかけてコロンビア交響楽団とモーツアルトの後期交響曲やブラームスの第二及び第三、ブルックナーの交響曲第四番「ロマンティック」などを精力的に録音している。ワルターは自分に残された時間は極めて少ないと自覚していたに違いない。
さて、「大地の歌」は切札の作品なので、寄せ集めのコロンビア交響楽団ではなく、1956年のシューベルトの「未完成」交響曲の録音と同様、ぜがひでもニューヨーク・フィルでとプロデューサーのジョン・マクルーアに掛け合ったに違いない。
引退前の1956年から58年にかけて、ワルターはニューヨーク・フィル定期で数々の名演奏を産み出した。それらは故皆川達夫氏の文章で綴られている。「未完成」、モーツアルト「レクイエム」などなど。
そして1960年、ニューヨーク・フィルとの最後の演奏会が行われ、シューベルトの「未完成」交響曲とこのマーラー「大地の歌」が演奏された。これもマーラー生誕百年祭の一環としてのコンサートであった。このコンサートに合わせて商業録音されたのが当該録音である。ニューヨーク・フィルとしても当時ディミトリ・ミトロプーロスやレナード・バーンスタインはさて置き、マーラー直伝の大指揮者ワルターの下でマーラーの作品を演奏するという光栄に浴するという、またとない機会であったに違いない。
だが、ニューヨーク・フィルのメンバーによるワルターの評価は芳しいものではなかった。例えば、ある楽員による「ワルターが我々に教えうる音楽上の問題など何もないのだ、ということをワルターその人に教えるのに5年を要した」という記載を目にした時、指揮界の三大巨匠のひとりと信じていた私はショックを受けた。しかも、それが首席級メンバーの一致した意見だったらしい。
もう一つ、在米生活中(1980-81)、LPレコードは買わなかったが、カセット・テープは結構な数購入した。驚いたのは日本ではワルターの録音は廉価盤で売り出されることはほんとんど無かったが、米国ではOdyssey(CBSの廉価盤レーベル)で出ていて、「復活」もその廉価版であった。
コンサートの世界でも、コマースの世界でも芳しくないワルターの評価、むべなるかなである。
ワルターのようにヨーロッパの伝統に則って、内から湧き出る音楽、内面的演奏、そういったものは新興国、人種の坩堝のアメリカでの評価が高くないのは当然である。さらにユダヤ人という出目、トスカニーニやフルトヴェングラーように、王様然とは振れなかったはずである。
にもかかわらず、第二交響曲「復活」と「大地の歌」はニューヨーク・フィルとのステレオ録音で残されたのだ。めでたし、めでたし。
振り返ってみると、ワルターのマーラーは学生時代から親しんできた。
名盤の誉れ高い交響曲第一番の録音は学生時代に楽友K君が大阪「ワルツ堂」で買ったという第一番「巨人」のレコードを数人の音楽仲間で下宿の部屋で眺めていた。当時、オーディオ装置は誰も持っていなかった。「Giant」は俗っぽい巨人で、「Titan」は文学的な巨人なんや、とK君が京都弁で解説してくれた。
翌年、ようやくパイオニアのレコード・プレーヤーのキットを手に入れ、ダイアトーンP610Aを不細工な自作の箱に取り付け、何とかLPレコードが聴けるようになった。スピーカーは1台なので、ビクターのヘッドフォン・アンプをモノーラルのテープ・レコーダーに接続すると言う執念のセットであった。我がオーディオ事始めである。
レコードの方は当時、キングから廉価版MRシリーズというのが出ており、すべて1枚1、000円のモノーラル盤で、買い込んだMR盤の中にマーラー「大地の歌」が含まれていた。名盤の誉れ高きワルター&ウィーン・フィル、そしてアルトがかのキャスリーン・フェリアー、テノールがユリウス・パツァーク、とくにその終楽章「告別」を毎晩のように聴いた。
それから、ワルター全集の分売でマーラー交響曲第九番のリハーサル盤、CBSがソニーに移ってから出たワルター全集のマーラー編、これは立派な化粧箱に入っていた。当時マーラーはワルターという既成概念みたいなものが出来上がっていて、ワルターの指揮に何の疑念も持っていなかった。CD時代に入り、ワルターのマーラー交響曲選集のBOXを購入した。
しかしながら、これらの演奏を聴きながら、ワルターは誰もが違和感を覚えないように、広く受容されるようにという、いわば「啓蒙的姿勢」で取り組んでいたのではないだろうかと考え始めた。そのような配慮が底にあるような気がし始めたのである。そして、私はマーラーの激情や異形や特異性を、凹凸をなだらかな方向に丸めたようなワルターの指揮に疑念を持つようになった。「古典」の延長にあるような、そんなかなり「無毒化」へとシフトしたマーラー。そして、何よりも前衛的、闘争的なマーラーとは逆で、穏健な気質で外面的な演奏を嫌うのがワルターなのである。
それはともかく、上述した疑念はマーラーを実際にコンサートで聴き始めたことに起因する。
最初の経験がバーンスタイン&ニューヨーク・フィルの大阪公演で、マーラーの第五交響曲がメイン・プロであった。冒頭のトランペット・ソロに続くトュッティ、身の毛がよだつような響き、思わずハイデルベルクの山手墓地のドームあたりの、人気がなく、カラスが飛び交う不気味な風景(そこはフルトヴェングラーのお墓参りに行ったのだが)が頭をよぎった。加えて、第一楽章コーダの鉛が落ちて来たような総奏。そして、そこからのバーンスタイン的、アメリカ的にアグレッシブな展開に圧倒されてしまった。
当時、私はまだ若く、梶本音楽事務所に直接電話して追加席を確保し、勤務地福山から大阪に出向いたのである。フェスティバル・ホールの追加席にようやく辿り着き、横を見るとイツアーク・パールマンが座っていた。
さらに、1981年シカゴでアバド指揮シカゴ響による第一交響曲を聴いて、この作品観が一変してしまった。あのスーパー・オーケストラを極限まで追い込んだような、豪快な演奏。同年9月、ニューヨークで聴いたメータ指揮ニューヨーク・フィルによる第二交響曲「復活」も凄かった。ソロはキャスリーン・バトルとクリスタ・ルートヴィッヒであった。とりわけ、終楽章の合唱の中の荘厳な響きの中に浮かび上がるバトルの美声にはしびれてしまった。
その間、春にウイスコンシン大学の大学オケがマーラーの第六交響曲を演奏した。私はショックを受けた。コンサートは2回繰り返され、2晩目はヤーノシュ・シュタルケルのリサイタルだったが、途中、「アルペジョーネ・ソナタ」が終わるや否や、コンサート会場ミルズ・ホールへ一目散走り、第六交響曲のフィナーレを聴いた。そして、2回目のノック・アウトを経験した。
「大地の歌」に戻って、この作品はご存じのように李白、孟浩然など四人の唐時代の詩人の作品を訳した、ドイツの詩人ハンス・ベートゲの「支那の笛」から採られているのだが、ベトゲは中国語の原典から直接訳した訳ではなく、ハンス・ハイルマンによる「中国抒情詩集」をベースにしており、さらにこれも中国の様々な詩を集めたものらしい。
マーラーの晩年は長女の死に始まり、宿痾の心臓病、ウイーン宮廷劇場指揮者の解任、妻アルマの不倫と立て続けの不幸に襲われ、こういう「厭世的な東洋の詩」にすがったのであろう。
ウィーンを蹴って、新大陸に活動を移そうとしていた時期なので、「大地の歌」に漂う東洋の響きはヨーロッパとの決別の意図が含まれていたのかもしれない。
さて、結構長い間離れていたマーラー「大地の歌」、数年前から再び聴き始めることになった。それはCD棚を整理中、標記のワルター&ニューヨーク・フィル盤が見つかり、懐かしくなってトレイに載せたことに始まる。
長い間聴いてきたワルター&ウィーン・フィル盤も近年、DECCAの公式録音の間に行われたライブ録音盤までCD化されている。さらに、クレンペラー盤の最後の録音の重みも深く受け止めている。
しかし、現在一番取り出すことが多いのはやはりワルター&ニューヨーク・フィル盤である。
ワルターの内面性と、マーラーの晩年の「諦観」が相加効果となって、実に味わい深いパフォーマンスとなっている。
ソリストはミルドレッド(マイルドレッドと発音すべきではないだろうか)・ミラーのアルト、エルンスト・ヘフリガーのテノール、1960年録音で、ニューヨーク・フィルとの最後の録音となった。上述したように、収録場所はニューヨークのマンハッタン・センター、4月18日及び25日録音とある。ワルターの体調(心臓の病)を考慮しての日時設定だったのだろう。この生誕百年祭のミトロプーロスやバーンスタインのコンサートは1、2月に行われているので。
強者揃いのニューヨーク・フィルのメンバーもこの作品の初演者、既に2回の公式録音があるとなると、さすがにワルターの棒に抗うこともなく従ったに違いない。
定期演奏会でのソリストはモーリン・フォレスターとリチャード・ルイスであったが、契約上の問題で、しかも二人はRCAにライナーの「大地の歌」に起用されたので、使えなかったらしい。
それからずっと前、即ち1948年1月の定期演奏会でもこの「大地の歌」を振っているのだが、この時のソロはアルトがあのキャサリン・フェリアー、テノールがセット・スヴァンホルムである。
1960年というのは米国では動きが激しい時で、ニューヨーク・フィルはもう常任指揮者がバーンスタインに代っていた。CBSではバーンスタインによるマーラーの交響曲全集が検討されていて、一方、ワルターはもう全集をやるような気力・体力も残されておらず、若くアンビシャスなバーンスタインは「巨人」も自分に振らせてくれと言っていたらしい。ワルターは内心穏やかざるものがあったに違いない。
しかし、とりあえず録った、ワルターがコロンビア響を振った録音を聴いて、バーンスタインは自分にはまだ振れないと降参したらしい。
「大地の歌」に戻って、ワルターのこのニューヨーク・フィルとのステレオ盤、ミラーにヘフリガー、ともに健闘している。いや、私は声楽部分よりこの作品の肝は終楽章「告別」のあの長い、長い間奏部分と考え、また一番好きなところなので、何の不満もない。まあ、ヘフリガーは少し気が抜けている感があるが。
また録音の声が突出しないように録られていて、いいバランスである。この録音のプロデューサーはジョン・マクルーアである。
まだ数枚、CD棚にはこの作品のディスクが並んでいるけれども、何回も繰り返すのだが、結局ワルター&ニューヨーク・フィル盤に落ち着く。
ただ、1936年のワルター&ウィーン・フィルによるこの作品のライブ録音はナチが政権をとった1933年の数年後なので、ケルステン・トルボルイ(Ms)とリチャール・クルマン(T)は仕方ないとしても、どの録音もネイティブとしてドイツ語を発声するソリストのコンビではないのが気になる。フェリアーの歌唱はよく批判的に評価されているが、純粋なドイツ人、もしくはドイツ語圏内の歌手が少ないのが不思議である。モーリン・フォレスターはワルターがよく登用したアルトであるが、カナダ人である。私は彼女がそんな格の高い歌手とは思ってもいなかった、ドイツ語の発音は正確だったらしいが。
というのも、滞米時住んでいたマディソンの交響楽団、これは我が国の雑誌には登場したことがないオーケストラなのであるが、そこでの定期演奏会のソリストに選ばれていたからである。ただ地方のオケとは言っても、アリシア・デ・ラローチャ(Pf)、ルッジェーロ・リッチ(Vn)も登場し、前者はブラームスのピアノ協奏曲第二番、後者はベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲を無難に好演していた。
「大地の歌」では映像でも印象に残っているものがある。リハーサルなのだが、バーンスタインがイスラエル・フィルを振った際の映像で、慌ててビデオ・カセットに収録した記憶がある。横で見ていた長女が指揮するバーンスタインを観て、「ゴリラみたい」と呟いたのが記憶にある。
「生は暗く、死もまた暗い」、青春時代でも老境に入っても、とてもアピールする詩だなと感じ入る。また、歌詞が寄せ集めの詩集というのがモザイク模様のマーラーの音楽にとてもフィットしている。とくに、第一楽章の「大地の憂愁を歌う酒の歌」というタイトルが酒呑みの私は気に入っている。
さて、この「大地の歌」においても夢のレコードに想いを馳せる。そのバーンスタインである。
やはりバーンスタインに尽きる。
ウィーン・フィルとの録音が1966年、イスラエル・フィル盤が1972年、そこでお終いなのである。それから20年近く生は残されていたのに、しかも最後の交響曲全集は1987年に完了しているのにである(第六番だけは映像音源から採られている)。「大地の歌」を加えようと言う意思はなかったのであろうか。晩年ではあるが、再度、深みを増したクリスタ・ルートヴィッヒを起用してということも可能だったはずである。
バーンスタインの晩年の録音にこの「大地の歌」が含まれていないのは甚だ残念である。返す返すも残念!しかし振り返ってみると、最初のニューヨーク・フィルとの全集にも「大地の歌」は含まれていなかった。マゼールと同様、交響曲としての扱いではなかったのだろう。
バーンスタイン&ウィーン・フィルによる晩年の録音、冒頭のホルンの咆哮や「告別」での間奏部、後者では音楽が止まりそうなテンポだったのではと想像するのだが、聴いてみたかった。