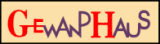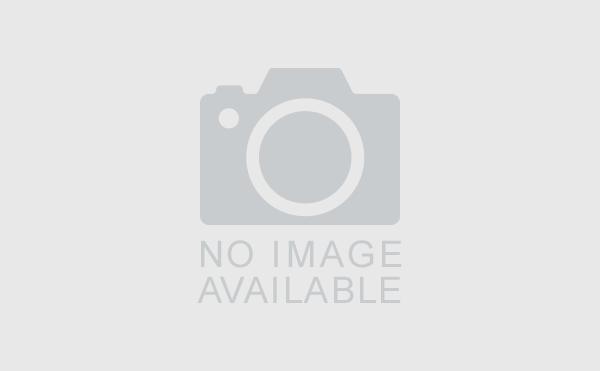シューマン:交響曲第四番ニ短調Op.120
あと千回のクラシック音盤リスニング(19)
シューマン:交響曲第四番ニ短調Op.120
〜 私にとっての“ロマンティック”交響曲、その現在の神盤 〜
シューマン:交響曲第四番 ニ短調Op.120
レナード・バーンスタイン指揮ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
(CD: DG 453 049-2 *全集)
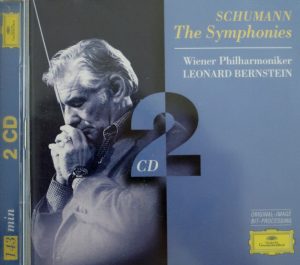
交響曲の中には堂々と、自作に自ら「ロマンティック」と表題を付けた作曲家も存在する。ブルックナーである。人気のあるシンフォニーで、フルトヴェングラーも度々取り上げた。いや度々どころではない。この作曲家の作品で巨匠が振った回数が最も多かったのは第四番「ロマンティック」である。しかし、しかしである。これってそんな傑作なのであろうか。
表題付きで、しかも親しみやすいため、巨匠はブルックナー普及という目的で選んだのではないだろうか。例えば戦前、英国でプログラムにブルックナーを組み込むのは困難を極めたそうである。なので、ブルックナー普及のため、「ロマンティック」で行こうというのが巨匠の戦略だったのでは。
それはともかく、「ロマンティック」という表題を、私はこのシューマンの第四交響曲に充てたい。思いっきり所謂「ロマンティック」な気分に浸りたい時、私はこのシューマン第四のレコードを取り出す。この作品は元々各楽章が連続して演奏されるので「交響的幻想曲」という標題が与えられていた。だが、私ならその標題はシューベルトの「未完成交響曲」に与えたい。
拙著「クラシック33名盤へのオマージュ」で私はこの作品を選び、そしてフルトヴェングラー&ベルリン・フィル盤を神盤として取り上げた。今でもこれは神盤に値すると考えている。巨匠と言えば魔法のような「テンポ操作」、鵜匠の名人が綱を神業でたぐり寄せるようなイメージが湧いてくる。そう、巨匠のテンポ操作は彼の最大の武器であったに違いない。一方、カラヤンでは「レガート」であろうか。
しかし1952年録音のモノラル盤、さすがに頭の中でイメージを膨らませて補わなければならないような録音となってきた。文字通り神棚に飾るような存在となってきたのである。
それで、巨匠の録音に代わって、私が現在最も引っ張り出す頻度が高いのはバーンスタイン&ウィーン・フィル盤である。いや、他の録音もあるにはあるが、このシンフォニーはバーンスタイン&ウィーン・フィルの独壇場と言ってもよい。学生時から神盤として崇めてきたフルトヴェングラー盤にとって代わるレコードが現れるなんて想像もしなかった。 それはそれとして、この作品の存在と価値を私に知らしめた二つの経験が蘇ってくる。一つのFMでの放送であり、今一つはTV映像である。
FM放送の方はNHKでの近衛秀麿氏がフルトヴェングラー指揮のこの曲の素晴らしさを藤美代子アナウンサー相手に語るというような番組であった。特に第二楽章のロマンツェの出だしからヴァイオリン・ソロに移る辺りまで、語る近衛氏は感慨にふけっているようだった。
そして、映像の方、それはバーンスタイン&VPOのロンドン公演、これはTVで観たものだった。夢のようなライブの放送で、少年のようなキュッヒルがコンマス(次席)として登場、指揮のバーンスタインはまだ若々しく指揮台上でジャンプを繰り返していた。
これは私がもう一度観てみたい映像のトップに来るものであるが、もう半世紀も前のこと、また例えば「レコード芸術」誌などでトピックとして現れないので、「幻の映像」と化していた。しかし、草津音楽祭でのクラシック音楽同好会の懇親会の場でこの映像の話をしたら、すぐにIさんがググって下さり、ちゃんと1972年に放送されたことが明らかになった。さらにNさんが、その放送の音声部分を聞かせて下さった。凄い!なつかしの大木正興氏の解説であった。
バーンスタインとウィーン・フィルは後年1984年にシューマンの交響曲全集を録音している。私は最初に第一番とペアーになった第四番のアナログ盤を買った。バーンスタインが巨匠となって、そのバーンスタインのポートレイトがジャケットになったLP、苦み走ったそのバーンスタインのポートレイトはそれ自体素晴らしい。そして、その録音も徐々にフルトヴェングラー盤にとって代わる存在となり始めた。そして、CDでの全集、さらに映像盤(マイスキーが聴衆として登場する)を得て、シューマン第四=バーンスタインという図式が出来がったのである。
フルトヴェングラー盤からバーンスタイン盤へ、この移行がスムーズに行った一つの理由はテンポの扱いであろう。スポンテーニアス、かつ幻想が熱く膨らむような入魂の指揮が目に浮かぶ。こういう作品ではウィーン・フィルのオペラで鍛えた表現力が物を言う。
だが、我が理想はフルトヴェングラーとべルリン・フィルの組み合わせである。ロマンティックな響きはやはりドイツの黒い森から生まれてほしい。ウィーン・フィルは流動的な表現は見事であるが、基本柔らかさが勝り、過熟である。
ベルリン・フィルの方はフルトヴェングラーの指揮で哲学的とでも言える雰囲気が加わるに違いない。あの旧フィルハーモニー・ザールでの楽員に魔法をかけているような指揮姿が目に浮かぶ。よくぞ、あのような素晴らしい指揮姿の写真が撮影されていたものだと思う。その写真を眺めながら、この巨匠のLPをターンテーブルに載せてきた。
そうやって、聴いてきたのだが、あの1953年の録音がライブであったらとも考える。しかし、巨匠の最高のスタジオ録音と言われているように、主観的と客観的のバランスが素晴らしい。これは一発録りに近く、しかも録音後、楽興が汲めど尽きせぬ程に湧いてきた巨匠はその余韻でハイドンの交響曲第88番を追加録音させたらしい。
これに関連して、ちっとも話題に上らないがシューマンの交響曲第四番のフルトヴェングラー、ルツエルン音楽祭でのライブ録音盤について。私はベートーヴェンの第九交響曲のルツエルン盤を購入する折、シューマンの第四を見つけ同時に手に入れた。気張ってSACD盤の選択である。
私はこの作品はベルリン・フィルしか、妥協してもウィーン・フィルしかお相手できないと想像していたのであるが、寄せ集めオケながら巨匠のライブでの録音が出たのには驚いた。ルツエルン盤は録音が今一なので評価が難しいが、アポロ的というか、贅肉が取れたというか、全体は端正で、爆発するような音は部分的にしか出ていない。フルトヴェングラー晩年の境地でもあるようだし、スイスのオケの特徴かもしれない。
しかし、テンポの変化もそう違和感はない。手兵のBPOであれば、などと無いものねだりをしなければいい演奏だと思う。
オーケストラとの絡みで言えば、この作品は米国のオケがいくら優秀でも、真の名盤は生まれないという気がする。ブラスの技術やメカニックがいくら優秀でも。
私は留学時に大学のオケでこの作品が演奏されるのを聞いたことがある。ウイスコンシン大学には音楽学部(music school)があり、指揮者もコメーという音楽雑誌にも名前が登場することもあった女性の指揮者ではあったのだが、まるでブラスバンド交響曲という演奏であった。いや、アメリカのオケでは無理というのは先入観かもしれない、セル&クリーブランド管やパレ―指揮デトロイト管の演奏を聴き直してみる必要がありそうだ。
この第四番は名指揮者たちの中にもこだわる人も多く、カラヤンもその一人である。しかしこの指揮者は基本的にロマンティストではないと思う、映像盤まで残しているのだが。クナッパ―ツブッシュでは十八番のレパートリーであったし、パレーのようなフランス人指揮者も振っている。そしてドイツ、ドイツしたコンヴィチュニー、サヴァリッシュ、そしてベーム。ザンデルリンクも彼の最後のコンサートでベルリン交響楽団でこの第四を振っている。時にイン・テンポのクレンペラー盤も聴くが、これはイン・テンポでもこの第四は素晴らしい、その確認のためだ。
「夢見るような表情で」という意味でブルーノ・ワルターもぴったしの指揮者だったかもと思うのであるが、SP時代には複数の録音があるもの、晩年は全く取り上げていない。フルトヴェングラーの強烈な演奏でやる気をなくしたか。
話変わって、最近二人の音楽評論家のこの作品に対するコメントが気になっている。
一人はかの宇野功芳氏、このシューマンの第四は暗くて耐えられないので(総集編でのレコード選では)取り上げないと評しておられる。もうお一方は田村和紀夫氏で、彼の著書「交響曲入門」でシューマンの第四はどんな演奏で聴いてもよくわからないのではないか、と書いておられる。そんな作品なのだろうかと訝しく思ってしまう。
それから、音楽史的にはこの作品は思わぬ副次的産物を産んだ。この第四交響曲を勝手に改定したと激怒したクララ、そのクララ・シューマンへのお詫びと愛を込めて作曲して贈ったのがブラームスの間奏曲Op.118の第2である。この短い作品に込めたブラームスの孤独とクララへの愛の深い、深い想い。涙なしには聴けない作品である、特に後半は。クララのお礼の書状も素晴らしい。音楽家同士だからこそ理解し合えた、長い交友を基盤とした深いコミニュニケーション!
締めで再び、バーンスタイン。シューマンの交響曲でバーンスタインの本当のフェイヴァリット・ピースは第二であろう。録音回数も一番多いし、死の年のPMFでも「最後のメッセージ」として取り上げてもいる。しかし、第四もとても素晴らしい。若い頃、ニューヨーク・フィルと録音したシューマンの交響曲全集ではそうとも思わなかったが、ウィーン・フィルを得ての録音は現時点でも神盤扱いとしたい。
但し、映像盤の全集はめったに取り出さない。それに楽想と私が期待するバーンスタインの表情や指揮姿は結構なギャップがあるし、そもそも音楽に集中するには映像なしの方がよい。
それはそうなのが、それでも映像によって想いを馳せることも少なくない。マイスキーの登場は別としても、例えばこの四番のみがコンサートマスターはヘッツエルである。冷静な彼の渾身の献身的リード。バーンスタインは彼に全幅の信頼を寄せていたのであろう。また、この作品の肝とも言うべき第三楽章からフィナーレへのブリッジ、そのニュアンス、おおロマンティック!そしてコーダへの突進!いや、なんだかんだ言っても映像もWunderbar!である。