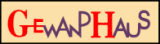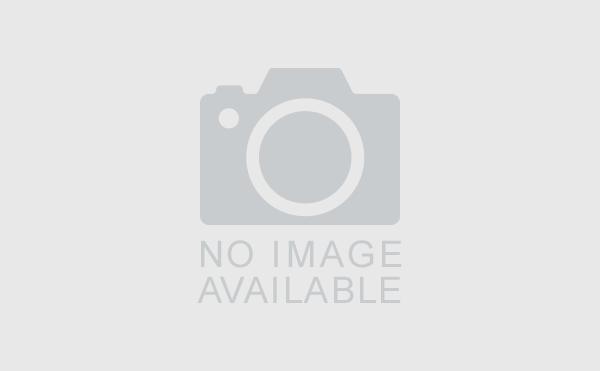ドヴォルザーク:弦楽五重奏曲第3番変ホ長調
後千回のクラシック音盤リスニング(21)
ドヴォルザーク:弦楽五重奏曲第3番変ホ長調Op.97
〜(続)ドヴォルザークの「アメリカン」はお好きですか?〜
ドヴォルザーク:弦楽五重奏曲第二番ト長調Op.77&弦楽五重奏曲変ホ長調第三番Op.97
ウィーン八重奏団員 CD: LONDON(DECCA) POCL-4239
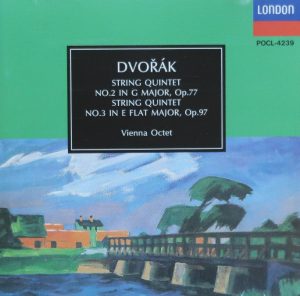
前回の「ドヴォルザークの弦楽四重奏曲“アメリカ”はそんなに名曲ですか?そんなに素晴らしいですか?」の続編である。
音楽之友社のONTOMO MOOK「クラシック名盤大全」(室内楽曲編)では夥しい数の室内楽の名盤が紹介されている。そこでのドヴォルザーク弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」の圧倒的人気で、「アメリカ」14に対し、ドヴォルザークのその他の弦楽四重奏曲0という結果が出ている。何ということだ、「アメリカ」がそんなに名曲ですか?と異議を唱えたくなって前号のコラムを執筆した。
前回、私はドヴォルザークの弦楽四重奏曲、もっといい作品があるだろうと第13番ト長調作品106を取り上げた。
さらに申し上げれば、もっといい作品があるのでは、とダメ押しをしたいのがこの弦楽五重奏曲変ホ長調である。「アメリカ」が前回書いたようにちょっと「躁的」な要素があるのに対し、この五重奏曲はもっと落ち着いた、腰が据わった名曲である。「アメリカン」の雰囲気を漂わせた室内楽の最高傑作と信ずる。なので、こちらが「アメリカン」として、世に出てほしかった。
まあ、四重奏曲は常設団体、五重奏となるとヴィオラかコントラバスを加えねばならないので、難しい問題が生じるのは分かるが。弦楽四重奏曲「アメリカ」に比べると、一聴して惹きつけるような旋律に欠けることも確かである。ちょっと地味なのである。
しかし、馬草の匂いはするが、「望郷」の念の深さ、アメリカ的要素の消化、どっしりした構成感で、こちらの方がもっといい作品として評価していただきたい、それが今回、私の言いたいことなのである。
どっしりとした構成感、それは楽器編成にも表れていて、弦楽四重奏にヴィオラが加わった形をとっている。私感ではあるのだが、ヴィオラよりもコントラバスの方がもっと二グロ的「どす黒さ」が出て、よかったのではと思うのであるが。というのは、この弦楽五重奏での前作第2番作品77はコントラバス版である。でも、コントラバスの扱いは難しい。第三楽章は懐かしさ満載のとても美しい緩徐楽章ポコ・アンダンテで、ユニークな趣きを醸し出しているのだが、第二楽章のスケルツォのような動きが顕著な楽章となると「鈍重」みたいな響きも現れる。イメージとして巨像が踊っているような。
この弦楽五重奏曲、私がこれまで親しんできたCDはウィーン八重奏団によるDECCA盤である。もう解説書が変色してしまったほどの長い付き合いである。1990年代半ば、秋葉原での衝動買いのCDなのだがまだ飽きることがない名盤である。
この録音ではヴァイオリンがアントン・フィーツ、第二ヴァイオリンがウィーン・フィルの顔とも言える存在であったヴィルヘルム・ヒューブナー、ヴィオラがギュンター・ブラテンバッハ、そしてチェロがアダルベルト・スコチッチという名手達が登場、五重奏で第二ヴィオラとしてヨーゼフ・シュタールが加わって錚々たるメンバーによる演奏となっている。ヒューブナ-さんは1974年3月、ウィーン・フィル定期のマゼール指揮「春の祭典」で、第二ヴァイオリンのセクションのトップとして顔を真っ赤にして奏いておられた。「マゼールめ、この野郎」だったに違いない。
ドヴォルザーク弦楽五重奏曲第3番に戻って、その録音は1971年4月である。私はこの団体が来日した1973年、福岡でモーツァルトのクラリネット五重奏曲K581とディヴェルティメントK287という最高のプログラムを聴かせてもらった。しかし、暖房が効きすぎた会場もあって、途中で寝入った記憶が残っている。罰当たりなことをやったものだ。
リーダーのフィーツはややアバウトなボスコフスキーとは異なり、ウィーン流ながらフレッシュでキリっとした繊細なヴァイオリンを奏し、K334やK287はじめ不滅の名演を残している。ウィーン・フィルのコンサートマスターになると皆ノイローゼになるそうで、繊細な神経を持ったフィーツはコンマスには適さなかったのであろう、歴代のコンサートマスターのリストには載っていない。
ところで、プラハは位置的にウィーンから国際列車で5時間程度、旧ハプスブルク帝国圏内で、ドヴォルザークの音楽にも自然と入って行けるような関係であったに違いない。ウィーンでは料理人はチェコ出身が多いと聞いた。
この弦楽五重奏曲の演奏も、チェコの音楽をウィーン風に典雅に仕上げたようなものとなっている。美しすぎるという評もむべなるかなである。しかし、「馬草」の匂い軽減にも貢献しているはずである。これは料理も同様で、例えば台湾料理での八角、これを好みのスパイスと取るか、一癖ある香りと取るかの差みたいな。
私はウィーン八重奏団のCDをずっと愛聴してきており、チェコのボヘミア・スタイルの演奏は聴いたことがない。「新世界より」もケルテス指揮ウィーン・フィルの名盤のみ、LP時代にはチェコ・フィルのレコードが2、3枚あったが。
「アメリカ」について、馬草の匂いを嗅ぎつけると書いてしまったが、この作品は「アメリカ」の完成後、ひと月かけて作曲され、言わば「アメリカ」と双生児みたいに作られた作品である。当然のことながら、共通の要素も多く、この作品にも同じ匂いを嗅ぎつける。実際、本作も「アメリカ弦楽五重奏曲」とか「アメリカ」と称されることもあるそうだ。だが、私には弦楽四重奏曲「アメリカ」よりもっと立派な作品に思える。繰り返すが、こちらを「アメリカ」と呼んでほしかった。
当時チェコ音楽紹介の旗頭であった故佐川吉男氏はが「アメリカ」とは異なる四重奏曲を推薦されていたのではと期待していたが、実際はスメタナ四重奏団の「アメリカ」の五度目の録音(1988年)だけで、それに驚いたことは前号で述べた。その佐川氏が唯一人この弦楽五重奏曲第三番を取り上げておられる。以って、めでたしめでたしである。
その佐川氏の推薦盤がヨセフ・スークが第一ヴィオラとして加わったスメタナ四重奏団による演奏である。これは未聴であるが、おそらく素晴らしい演奏であるにちがいない。ドヴォルザークは自身がヴィオラを弾いていたこともあるのだろうが、ヴィオラに対する思い入れがあるに違いない。スメタナ四重奏団盤では第一ヴィオラが御大ヨセフ・スーク、しかも佐川氏の評では「中でも素敵なのはスークの第一ヴィオラで、この楽器特有の官能的な音色と、ドヴォルザーク特有の憧れと哀愁の混じり合った抒情とを気品をもって生かしてゆく第三楽章の変奏の主題出し方などが絶妙」と評しておられる。さらにスークの加入によって、スメタナ四重奏団の演奏としては異例なほどのスケールの大きさらしいので、これは是が非でも聴かねばなるまい。
さらに、この盤の余白には「森の静けさ」の、ヨセフ・スーク編曲によるヴィオラとピアノのための版が併録されているという。これはジャクリーヌ・デュ・プレのドヴォルザークのチェロ協奏曲のLPで親しんだ作品である。何が何でも手に入れなくてはならないレコードである。しかし、現在は廃盤とのこと、この業界、商業主義に毒されていることを痛感する。