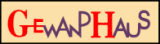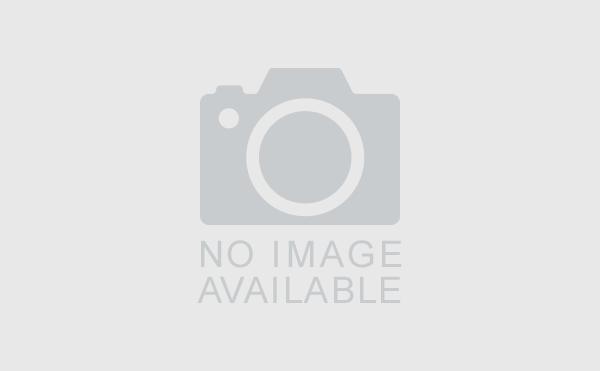ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第五番変ホ長調 Op.73「皇帝」
あと千回のクラシック音楽リスニング(39)
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第五番変ホ長調 Op.73「皇帝」
〜 フルトヴェングラー&フィッシャー、二人の巨匠による気宇壮大な名演 〜
EMI 9 07884 2(輸入盤)
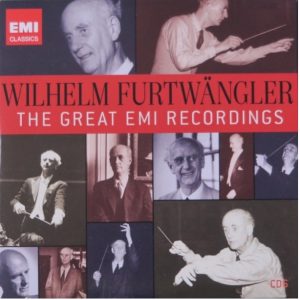
久しぶりに歴史的名盤をトレイに載せた。
エドウィン・フィッシャーの独奏、ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮フィルハーモニア管弦楽団によるベートーヴェン:ピアノ協奏曲第五番「皇帝」である。
巨匠によるベートーヴェンの交響曲の戦後の商業録音はすべてウィーン・フィルハーモニーなのに、この録音でのオケはフィルハーモニア管弦楽団である。それには理由があって、第二次大戦後の1951年2月、ロンドンのアルバート・ホールで両巨匠は共演し、その演目が「皇帝」だったのである。それにヴァイオリンのユーディ・メニューインとの協演もオケはフィルハーモニア管とルツエルン祝祭管である。
フィッシャーとフルトヴェングラーの協演であればピアノ協奏曲第四番であったならと思うのだが、あの広大なホールでは相性がよくないので「皇帝」が選ばれたのであろう。フィッシャーのアラが出やすいにもかかわらず、である。
歴史的名盤を久しぶりにトレイに載せたと書いてしまったが、これにも理由がある。私はこの名曲が嫌いである。せっかく第四番という傑作が出来上がったのに、その方向で深化型の作品が生まれるのではなく、何故こんな外面的で派手派手しい作品を書いたのかと考えてしまう。ピアノ・ソナタは最晩年、第28番から最後の32番に至るまで、内面的にも深化した名品を次々と生み出しているではないか。そういう流れで、「幽玄」な趣のピアノ協奏曲を創作してほしかった。
なので、この「皇帝」を聴いていると、何故か空しくなる。ピアノのメカニックな効果が強調されて、内省的な深い響きは部分的にしか現れないので。ベートーヴェンはこの作品73で限界を感じたのか、あるいは達成感に浸ったのか、これ以降、ピアノ協奏曲は書いていない。
さて、フィッシャーとフルトヴェングラー、両巨匠によるこの「皇帝」の演奏、気宇壮大、立派なものである。
冒頭は「エロイカ」と同様、堂々とした変ホの和音が響き渡る、と言いたいところであるが、何分1951年のモノーラル録音、さらにオケがフィルハーモニアなので、オーディオ的には貧相である。そこで、我が脳内イコライザーで補正して、つまり想像力で補って傾聴する。そもそもこの貧相なサウンド、これがよいのかもしれない。フリードリヒ・グルダ盤や、もっと遡ってヴィルヘルム・バックハウス盤のようにムジークフェライン・ザールでウィーン・フィルのサウンドがDECCAのステレオ録音で拡がる、そのような豊饒な音が再生されるとこちらの聴き方はどうしても受動的になってしまうのである。
そうやってこの歴史的名盤に耳を傾けると、やはり立派な演奏である。
フルトヴェングラーの指揮はいつもの通り素晴らしいものである。第一主題の提示、その展開、さすがである。
ただ、この時期、オーケストラはまだ巨匠の棒に慣れておらず、響きはやや貧血気味である。例えば、ホルンはかのデニス・ブレインが吹いていたはずであるが、朗々とした響きとは言い難い。翌52年に至ってこのオケと「トリスタンとイゾルデ」全曲を録音、巨匠は大満足し、忌み嫌っていたウオルター・レッグ(EMIのプロデューサー)に感謝の書状を送っている。
最晩年、このオーケストラは巨匠のお気に入りだったのかもしれない。死の年1954年、ロンドンとルツエルンで振っている。しかも、このコンビの最後の演奏がベートーヴェンの第九なのである。その第九、今ではバイロイト盤以上に評価する批評家も多い。
巨匠の指揮にフィッシャーも堂々と渡り合っていて素晴らしい演奏になっている。
続く第二楽章は本盤で最も素晴らしい目玉的部分であろう。期待通り、深々とした、内省的な緩徐楽章となっており、フィナーレのロンドも華麗ではあるが楽興に溢れた演奏となっている。
これがライブ録音であれば、フィッシャーのミスタッチでお蔵になっていたにちがいない、フルトヴェングラーは火のように燃えたかもしれないが。
そうフィッシャーは指が回らないピアニストだったようだ。かつて、「音楽を愛する友へ」という著書を読んでおり、しかもフルトヴェングラーの盟友、二人並んでスコアーを前に論議している写真があるほどである。何やら哲学的な雰囲気を醸し出す、ピアニストらしくないピアニストというイメージを作り上げていた。当時の愛聴盤にベートーヴェンの最後のピアノ・ソナタがあって、素人の私でも分かるようなミスタッチがあり、スタジオ録音でも無修正という鷹揚さに惚れたものである。
ところが、この録音ではそういった瑕も目立たず、ピアニストが評価すればどうなのかは分からないが、私には巨匠と堂々と渡り合った立派な演奏に聞える。そもそもこの作品で指が回り過ぎるというのも、この作品の風格が落ちるのではというような気もする。
昔はフィッシャーのようなピアノのメカニックから解放されたタイプのピアニストが結構いたようだ。その代表がアルフレッド・コルトーであろう。しかし、ミスタッチを上回る表現力があり、信奉者も多かった。コルトーは親ナチ派の筆頭であったが、ディヌ・リパッティなどユダヤ系の若手を育ててもいる。
ドイツではエリー・ナイ、ヴァルター・ギーゼキング、ヴィルヘルム・ケンプ、ヴィルヘルム・バックハウスと大物ピアニストには親ナチ派が多かったようだ、党員とまでは行かなかったものの。さらにアルトゥル・シュナーベルのようなユダヤ系ピアニストがナチ政権下では演奏できなかったので、上記のピアニストの登場回数も多くなり、フルトヴェングラーとの協演も増えた。しかし、大戦後は巨匠とこれらのピアニストとの協演は全く記録されていない。巨匠はナチとの関係でナーバスになっていたのであろう。戦後はフルトヴェングラーが最もお金を必要としていた時代で、シカゴ響との契約に飛びついたくらいである。これはアルトゥーロ・トスカニーニやユダヤ系アーティス達の猛抗議によって流れてしまったが。それはさておき、このフィッシャーとフルトヴェングラーによる「皇帝」はモノーラル録音ではあるものの、「皇帝」の名盤としてその評価は永久に失われることはないであろう。
フィッシャーはソリストとして最も多く巨匠と共演したピアニストである。協演した回数は63回にも及んでいる。但し、録音が残っているのはこの「皇帝」を除いて、ブラームスのピアノ協奏曲第二番の戦時中の演奏のライブ録音のみである。
戦前の録音ではオーケストラは伴奏として二流の指揮者が振るか、弾き振りであった。レオ・ブレッヒとか、戦前のジョン・バルビローリやジョージ・セルなどまだ彼らが二流だった時代にフリッツ・クライスラーやアルトゥール・ルービンシュタインなどの録音で登場している。なので、当然フルトヴェングラーとフィッシャーという巨匠二人の協演の録音は戦前には存在しない。
ベートーヴェンのピアノ協奏曲第五番「皇帝」はこの作品の性格からして、フルトヴェングラーは戦前に20回近く取り上げているが、戦後はたったの1回である。上記したように、1951年2月、ロイヤル・アルバート・ホールにおけるフィッシャーとの協演で、取り上げたCDはそれに先立ってアビイロード・スタジオで商業録音されたものである。
もっとも、フルトヴェングラー自身はベルリン・フィルとずっと前から英国に招待されており、その折、ドイツ国家の演奏はまだ禁じられていたそうであるが、英国国歌の後、何とドイツ国歌をいきなり振り始めたそうである。彼の信念か、あるいは政治音痴の露呈か、いかにもフルトヴェングラーらしいアクションである。
それにしても、戦後フルトヴェングラーとフィッシャーの協演が極端に減って1回のみというのは何かありそうである。両巨匠とも同じEMIに数々の録音を残しているのだから。
私の想像ではフィッシャーとヘルベルト・フォン・カラヤンとの関係に起因するのではと考える。フィッシャーはカラヤンのアーヘン時代からの親しい間柄で、第二次大戦後、ナチ問題で苦境に立たされ、イタリアに潜伏していたカラヤンにフィッシャーは気前よく資金援助を行った。
それが巨匠の耳に入らないはずがない。巨匠は大音楽家なのだが、異常に嫉妬深かった。とくにカラヤンに対する嫉妬は度を越していた。
そう考えると、一度だけのフィッシャーとの戦後の共演は貴重な機会であり、この「皇帝」の録音も重みを増して来る。
フルトヴェングラーの名盤として度々登場するルガーノ音楽祭でのモーツアルトのピアノ協奏曲第20番ニ短調K466のライブ録音、これは当初、フィッシャーが演奏する予定だったらしい。イヴォンヌ・ルフェビュールはピンチヒッターだったのだ。
この演奏は巨匠の死の年1954年に行われた。オケがベルリン・フィルなので、余計に重々しく悲劇的なサウンドが鳴り渡る。巨匠とこのオーケストラの演奏に最もふさわしいのはやはりフィッシャーであろう、ルフェビュールも健闘はしているが、どうしてもピアノ付き交響曲のように響く。
どうしてフィッシャーはキャンセルとなったのか分からないが、巨匠の最後のツアーなのでフィッシャーに協演してほしかった、盟友として。さらに第24番ハ短調を偏愛する私は夢のレコードのトップにこの両巨匠の協演を挙げたい。K491はフィッシャーの十八番だったのだから。ただ、これは全く夢の話で、巨匠はどうしたことか、K491は生涯一度も振っておらず、お気に入りは第23番K488であった。
「皇帝」に戻って、歴史的名盤には興味深い組み合わせが目白押しである。ウラディミール・ホロヴィッツ/フリッツライナー、ヴィルヘルム・バックハウス/クレメンス・クラウス、グレン・グールド/レオポルド・ストコフスキーなどなど。かつてはバックハウスとハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮ウィーン・フィルによるLPの全集を聴きまくり、食傷気味になってしまったが、第一番なんてとてもよい。第一番は他にもスヴャトスラフ・リヒテル、フリードリヒ・グルダ、アルトゥーロ・ヴェネデッティ・ミケランジェリ、マルタ・アルゲリッチなど名盤目白押しである。この第一番は武満徹にとっても第四番に次ぐ存在だったようだ。
第五番「皇帝」はさすがに曲想からして女性ピアニストによる演奏は多くはない。例外は日本人女性ピアニストで、内田光子はじめ結構な数の録音がある。
アルゲリッチはベートーヴェンの第四協奏曲は自分よりうまく弾く人がいるので弾かないと宣うた。さすがのプライドである。「皇帝」ははなから彼女が弾くリストに入っていないに違いない。まあ、そういう作品なのであろう、「皇帝」は。閃きで勝負するような作品ではないのである。
嫌いな作品なので、また学生時代に聴きすぎて食傷気味なのが重なってめったにトレイに載せることはないが、強いて挙げればアルフレート・ブレンデルのソロ、ジェームズ・レヴァイン指揮シカゴ響のCDか。組み合わせも興味深いが、何よりとても楽興に富んでいる。