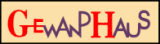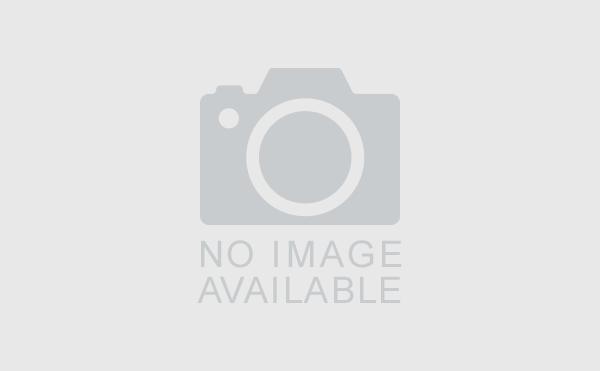ラフマニノフ:チェロ・ソナタ ニ短調 OP.19
あと千回のクラシック音盤リスニング(42)
ラフマニノフ:チェロ・ソナタ ニ短調 OP.19
〜 ロシアの“憂愁”とロマンティシズムを味わうためのチェロ・ソナタ 〜
CD: ユーリ・トゥロフスキー(Vc)、エドリナ・ルバキナ(P)
Chandos CHAN 8477
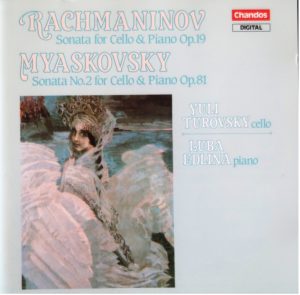
セルゲイ・ラフマニノフと言えばピアノ協奏曲第二番、交響曲も第二番、そのラフマニノフにチェロ・ソナタなんてあったかな、と思われる方も多いであろう。
それがあるのである、れっきとしたチェロ・ソナタが。
そもそもラフマニノフは本来ピアニスト、しかもヴィルトゥオーゾ的大ピアニストであるので、ピアノ曲が多いのは当然である。ピアノ曲では協奏曲以外にも、大作ソナタ第二番や人気の前奏曲集などが有名である。しかし、目立たない存在ではあるのだが、チェロ・ソナタを書いている。
ラフマニノフにとって室内楽と言うのは得意な分野ではなかった。なかったのだが、そもそも最初期にはロシア式に大作曲家チャイコフスキーの死に際し、結構有名なピアノ三重奏曲「悲しみの三重奏曲」Op.9、そしてもう一曲「悲しみの三重奏曲」(作品番号なし)と2曲のピアノ三重奏曲を書いている。この2曲はセットでボロディン・トリオ(Chandos)やボザール・トリオ(Philips)の演奏で聴くことができる。若書きでもちゃんとラフマニノフらしい作品に仕上がっている。
そして、今回のテーマのチェロ・ソナタである。この作品は私の愛聴曲の一つであり、実際の演奏が聴きたくて、チェロの師匠に演奏をお願いしたほどの作品なのである。
作品番号は19で、つまり有名なピアノ協奏曲第二番の次に作られた作品ということになる。
交響曲第一番の初演失敗に起因する精神的不調に悩まされたラフマニノフ、精神科医ダーリ博士による催眠療法等を受け、かのピアノ協奏曲第二番で大成功を収めるほどに回復した。めでたし、めでたし!「鬱からの脱却」、そしてこのチェロ・ソナタ、そういうタイミングの作品なのである。
では、何故チェロ・ソナタ? こういう場合、必ず作曲家にインスピレーションを与えるキーパーソンが現れるもので、クラリネットでいえば、モーツアルトではアントン・シュタードラー、ブラームスではリヒャルト・ミュールフェルトという具合に。この作品の場合、アナトーリー・ブランドゥコーフというチェリストの友人の存在があり、彼は上記の二つピアノ三重奏曲の初演でチェロを担当していた人物でもある。さらに、このメランコリックで、ロマンティックな楽想、淡い恋を感じていた女性がいたはずである。ともあれ、ラフマニノフによる数少ない室内楽曲である、このチェロ・ソナタは。
大ピアニストによるチェロ・ソナタの作品というと、かのショパンの前例がある。
ショパン晩年の作品であるが、私にとってショパンという作曲家はかなり苦手な存在である。交響曲も書けない作曲家はそこで尊敬の対象たりえなくなる。自分勝手な判断基準とは承知しているけれども。
しかしながら、ショパンのチェロ・ソナタはかなりいい線を行っている。何というか、この作曲家にしては構成がしっかりしていて、重厚で、しかも厳しい音楽である。ただ、時々現れるピアノのいかにも感覚的で美しい(を通り越して華麗な)旋律、これでやはりショパンの音楽だなあ、と納得してしまう。晩年の、しかも新しい分野への挑戦みたいな音楽であることは認めるに吝かではないのだが。
このショパンのソナタは結構人気があり、名曲と評価する人も多い。さすがにカザルスは奏いていないが、レコードの数は多く、フルニエ、デュプレ、マ、ロストロポーヴィッチなどの名盤が知られている。ロストロポーヴィッチ盤でのピアノはアルゲリッチである。この恋多き二人の協演は興味深い。何せ、アルゲリッチの何番目かの娘の父親はロストロポーヴィッチと言われていたほどである。二人の協演はミューズ=エロスの様相を呈する。かつて、つくば市の図書館で「ガリーナ自伝」というロストロポーヴィッチ夫人ヴィシネフスカヤの自伝を読破したことがあった。その中に、彼女をスラヴァ(ロストロポーヴィッチ)が略奪する場面が出て来る。マリア・カラスをオナシスがメネギーネから奪い去るのと相似形のシーンである。
私は西洋人のエネルギーの凄さを感じずにはいられない。草食民族と動食民族の根本的な差みたいな。奪われた亭主の方は精神的に大丈夫なのかなと、凡人的発想に陥ってしまう。
音楽からそれたようだ。
そういう訳で、ラフマニノフのチェロ・ソナタはショパンのそれとよく比較され、さらに両曲を同時に収録した音盤も多い。
様々な点でラフマニノフがショパンのチェロ・ソナタに倣ったのは間違いないだろう。しかしショパン以上に、ラフマニノフの曲の方が「抒情的」な楽曲に仕上がっていると、よく解説などでは書かれている。私の印象ではラフマニノフの方はやはり若書き、素直な抒情性が魅力的であり、上記したようにショパンの方は最期の作品で構成的という印象である。ラフマニノフのソナタはロストロポーヴィッチが若い頃録音しているが、再録音はしていないところにこのチェロ・ソナタ特質が表われているように思う。
チェロが憂愁の旋律を奏でると私の涙腺はすぐに緩んでしまうが、この作品はト短調、遅れて来た作曲家ラフマニノフ特有のメランコリックでロマンティックな旋律に「ロシアの憂愁」が加わって、とても魅力的な作品に仕上がっている。
この大ピアニストが作ったチェロ・ソナタ、作曲者はピアノは単なる伴奏ではなく、チェロとピアノが対等な関係にあることを強調したかったようだ。このため、初版は「ピアノとチェロのためのソナタ」と題されている。難易度から言うと、チェロのパートはピアノに比べると比較的易しく書かれているのではと考えている。なので、ヴィルトゥオーソ・タイプのシュタルケルはこのソナタを奏いておらず、ロストロポーヴィッチも上記したようにモノーラル時代に一度録音したのみである。
この作品の肝は第三楽章のアンダンテで、それだけ抜粋して演奏されたり、あるいは様々な低音楽器用に編曲して演奏されて演奏されたりしている。いわばラフマニノフの「ヴォカリーズ」に準ずるような扱いをされているのである。実際、第三楽章はこの曲の白眉、核心でもあるだろう。ロシア・ピアニズムの大教授であり、何度もこの曲の伴奏ピアノを弾いたコンスタンチン・イグムノフは、第三楽章について「ラフマニノフの抒情性の一つの極致である」と語ったそうだ。
しかし、私は第一楽章のロマンティックな旋律が一番好きである。この初々しい、ロシア的ロマンの飛翔!素晴らしい。
このチェロ・ソナタはかっては録音が少なく、エドモンド・クルツのチェロ、かのウィリアム・カペルのピアノによる1947年の演奏が最初の録音となるようだ。録音はその後、ぽつりぽつり状態だったが、1990年代に入って急に人気が高まり、現在はゴーティエ・キャプソン(ピアノはユジャ・ワン)盤まで多数出ている。
私は一時期秋葉原の石丸電気でCD漁りをやった時期があり、その折見つけたチェロがユーリ・トゥロフスキー、それにエドリナ・ルバキナのピアノという組み合わせ、つまりボロディン・トリオのメンバーによるChandos盤が未だお気に入りの1枚となっている。
演奏もさることながら、このレーベルの室内楽の録音は最高である。それに、このCDにはニコライ・ミヤコフスキーのチェロ・ソナタ第二番が併録されている。ミヤコフスキー、あの27もの交響曲を書いた作曲家である。これが難解なチェロ・ソナタかと思いきや、まるでシルクロードをラクダの背中に乗って、いい空気を吸って旅しているような、親しみやすい音楽なのである。ロストロポーヴィッチに捧げられた作品らしいのだが、大チェリストは苦笑いしながら弾いたのではと想像してしまう。
ラフマニノフのチェロと言うと、原曲はチェロではないのだが、よくチェロに編曲される作品に「ヴォカリーズ」がある。
かつて楽友Tさんに習って始めた、66の手習いのチェロ、なので私のチェロへの思い入れはとても強い。そのチェロの最終目標はこの「ヴォカリ-ズ」か、バッハBWV639「われ汝に呼ばわる、主イエス・キリストよ」のチェロ編曲版であった。
さて、ロシアへは3回訪れた。2回目はまだソ連時代で、上司の鞄持ちだったが、国賓に近い待遇で参事官がモスクワを案内して下さった。その折、レニンスキーという画廊ではサケ・マス交渉団の人達の購入は豪快で、あの壁からこの壁まで全部みたいな注文だったらしい。
私はプラスチンキ(レコード店)で、CDが見つかったら全部買いなさいと言うアドバイスを受けた。グラズノフの交響曲全集やラフマニノフの作品集数枚といったものだったが、後者の中に「ヴォカリ-ズ」が入っており、帰って鳴らしてみるとスヴェトラーノフによるピアノ独奏版であった。ピアニストとしてのスヴェトラーノフの初体験であった。
因みにこのロシアの旅ではレニングラード(現:サンクトペテルブルグ)でオペラやコンサートにも接することが出来た。マリンスキー劇場ではチャイコフスキーの凄絶なオペラ「マゼッパ」を、フィルハーモニーではレニングラード・フィルの定期演奏会に聴くことが出来た。
ラフマニノフのチェロ・ソナタに戻って、ロストロポーヴィッチはステレオ時代になってラフマニノフのチェロ・ソナタは録音していないのであるが、ショパンの方のソナタはアルゲリッチとの協演盤がある。そこで、もう化石的な夢の協演となってしまうのだが、この二人によるラフマニノフのチェロ・ソナタの演奏を聴いてみたかった。何せアルゲリッチは結構なロシア音楽ファイルで、ピアノ協奏曲第三番の名演はじめ結構な数のラフマニノフの録音がある。トゥロフスキー&ルバキナ盤の室内楽的演奏とは対照的な、スケール大きく、表情豊かなチェロ・ソナタが聴けるのではと夢は羽ばたくのである。しかし、この作品の持つ初々しいロマンは消し去られてしまうだろうか。
それはさておき、ラフマニノフのリサイタルでは終演後、とあるご婦人により必ず一輪の白い薔薇がステージに置かれていたそうである。ピアニスト冥利に尽きるであろうエピソードである。