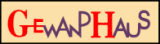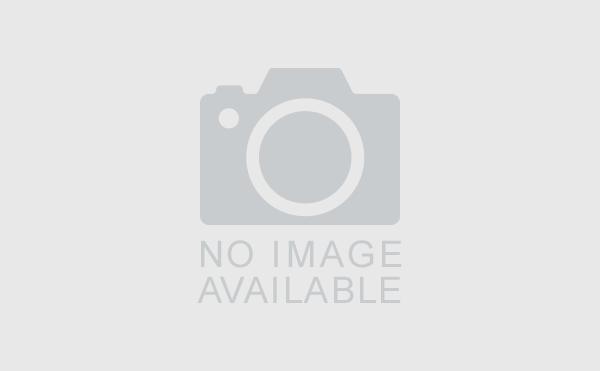ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調
後千回のクラシック音盤リスニング(23)
ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調
〜 たおやかそのもの、我が最愛のヴァイオリン協奏曲にしてオーディオ・チェックCD 〜
ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調
アルテュール・グリュミオー(Vn)、エド・デ・ワールト指揮
ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団
CD: PHILIPS PHCP-9629
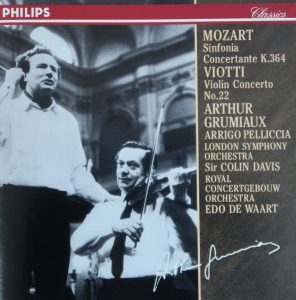
ベートーヴェンもブラームスもヴァイオリン協奏曲は1曲しか創っていない。いずれも大作にして傑作、ヴァイオリンを愛する私にとっては超傑作である。
一方で、そういう大輪の花のような大作ではないものの、例えば、尾瀬で見つけた美しい野草のような魅力的な、そして私が愛してやまないヴァイオリン協奏曲がある。その代表がこのヴィオッティのコンチェルトの第22番である。
とは言うものの、このヴィオッティのヴァイオリン協奏曲第22番イ短調は凄い作品なのである。まずベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲創作に多大な影響を与えた。それどころではない、ヨアヒムとブラームスが好んで演奏したことで知られる名曲であり、ブラームスに至ってはベートーヴェンのコンチェルトよりこのヴィオッティを評価していたらしいのである。また、ヨアヒムはカデンツァまで作曲している。さらにクライスラーやヴィニャフスキーなどもカデンツァを作曲した。
一方で、通常コンクールや発表会で学生演奏家が頻繁に採り上げる作品なので、ヴァイオリンのプロフェショナル的演奏家はこの作品を演奏するのはプライドが許さないであろう。ハイフェッツとかクレーメルがこのヴィオッティを演奏する姿は想像できない。
ヴィオッティはハイドンより少し遅れて、北イタリアのピエモンテ州で1755年に生まれた。つまりハイドンとほぼ同年代ということになる。私はハイドンよりずっと前の作曲家と勘違いしていた。ヴィオッティはそれまでのヴァイオリン独奏主体の協奏曲からハイドン・サイズのオーケストラとの協奏と試み、従属的な地位にあった伴奏をそれと同位に引き上げようとした点で近代協奏曲への先駆けと評価されている。
そういう講釈はさて置いて、何はともあれ、このコンチェルトはチャーミングそのもの。ヴァイオリンの魅力たっぷり、水も滴るようなヴァイオリンの音が満喫できる曲なのである。
まずテュッティで始まる長大な前奏が演奏される。そして、オーケストラに導かれて登場するやや哀愁を帯びたヴァイオリンのソロ、その気品、唯々「たおやか」という言葉がぴったしである。
しっとりとした情感が全体に漂うが、とりわけ第二楽章は安らぎを感じる楽章で、モーツアルトのクラリネット五重奏曲のラルゲットと双璧の音楽に聞こえる。
そして、ロンド形式の第三楽章は上記したようにべートーヴェンやブラームスへの影響が実感として感じられる楽章となっている。とくにブラームスのハンガリー風メロディの展開にその影響を感じ取ることが出来る。
さて、この作品との出会いは偶然であった。かって、モーツアルトのヴァイオリン協奏曲の全集が欲しいけれども購入に至らず、日本フォノグラムのフィリップス・レーベルからパイロット・シリーズという各アーティストの代表的な演奏のサンプル盤のようなレコードが廉価盤として出た。その中にグリュミオーとデイヴィス&ロンドン交響楽団によるモーツァルトの協奏曲第三番があって、とりあえずそれを手に入れた。そのレコードのB面に入っていたのがこのヴィオッティの第22番の協奏曲なのである。
このシリーズはイ・ムジチやホリガーの名盤も含まれており、イ・ムジチによるヴィヴァルディのイ短調のコンチェルトも短調好き人間の私には忘れ難き名演であった。
それはともかく、余白埋めにしても何故このヴィオッティのコンチェルトが選ばれたのであろうか。私はこのLPレコードを企画した方に心よりお礼申し上げたい。このパイロット・シリーズのLPを手に入れなければ、このヴィオッティという作曲家も、この22番目のコンチェルトも生涯出会わなかったかもしれないのである。いや、ヴァイオリン好きの私は若い頃、古今のヴァイオリン協奏曲全曲を網羅してやるぞ、みたいな壮大な計画も考えていたので、聴き逃すことはあり得なかったであろうが。
数回ターンテーブルに載せて、私はこのヴィオッティの協奏曲の虜になった。モーツアルトのヴァイオリン協奏曲第三番を聴くために買ったレコードにも拘わらず、いつの間にかB面のヴィオッティの方に嵌ってしまったのである。また、オーディオもエレクトロ・アコースティック(ELAC)STS-455Eというカートリッジをヴァイオリンのレコードの再生に使っていて、艶っぽいヴァイオリンの音が聴けてハッピーな時代であった。
そして、オーディオでのヴァイオリンの音のチェック用としてこのLPを使ってきた。
それからCD時代となり、モーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調K364との組合わせのCDもオーディオ・チェック用として重用してきた。K364ではヴァイオリンとヴィオラの定位、音色のコントラスト、ヴィオッティではヴァイオリンの音色をじっくりと試聴する。
ヴァイオリニストとしてのヴィオッティは、フランスのヴァイオリン奏法に強い影響を与え、フランコ・ベルギー奏派の開祖と見做されることもある。
フランコ=ベルギー派の正道を行くグリュミオーの演奏が名演となるのも、自然な成り行きであろう。グリュミオーのストラッドの愛器「ティシアン」か「デュポン」か、いずれにしても素晴らしい美音が奏でられる。
バックはエド・デ・ワールト指揮のロイヤル・コンセルトヘボウ管で、出だしのテンポが凄くよく、音楽性満点である。
この指揮者、素晴らしい才能だと思うのであるが、童顔が災いしたか、コンセルトヘボウ管でハイティンク時代副指揮者を勤めたにも拘わらず、指揮者歴を調べると超一流オケのシェフには就いてはいない。ロッテルダム・フィル、ミルウォーキー響、ミネソタ響、香港フィルなどなど。オペラもワーグナーやR・シュトラウスが手の内に入っているというのに。
私は彼がサンフランシスコ響の常任時代、一度だけ彼の指揮に接したことがある。
留学時、帰途、日系人にして大物の植物病理学者と会うため、カリフォニア大学デーヴィス校を訪れた際、サンフランシスコに滞在したが、そこでデ・ワールトが指揮するコンサートに行く機会があった。彼は現代音楽への取り組みも評価されているが、そのコンサートでもティペットの新作の世界初演が含まれていて、ティペット自身もステージに登場し万雷の拍手を浴びていた。メインはベルリオーズ「幻想交響曲」で熱いサウンドを新設なったデーヴィス・ホールに響かせていた。
サンフランシスコには数日滞在したが、有名なチャイナタウンで、地元の人に教えてもらった巨大なレストランで中華料理を堪能できた。そこでの中華系の人達の賑わいの中で料理を楽しむ様を眺めて、東西でかように食のマナーが異なるのかと驚嘆した。
また、観光スポットのフィシャーマンズ・ワーフでカニや生のクラムを賞味したが、隣のテーブルのロブスターが美味しそうで、翌日はそれを注文したものの、ロブスターは見掛け倒しで、カニは姿は冴えないが、どこでも最高に美味であることを確認した。
しかし、後年国際学会でカナダのシャーロット・タウンを訪れた折、レセプションで巨大なメイン・ロブスターが一人一尾供されたがこれは最高に美味であった。
音楽に戻って、ヴィオッティのコンチェルトはオイストラフとかスターンとか巨匠達も録音しているにも拘わらず、一向に人気が上がらない。英国ではどうなのかと、ペンギンCDガイドブックを捲ってみる。結果は何ということだ、第13番イ長調のCDが1枚記載があるのみ。驚きの結果である、第22番が落選とは。
このヴィオッティではもう1枚愛聴CDがある。ローラ・ボべスコの独奏、バックはなつかしいクルト・レーデルの指揮、そしてオーケストラはライン・パラティナ国立管弦楽団(ライン国立フィルハーモニー管弦楽団)という珍しい組み合わせである。
これも、このたおやかなヴァイオリン独奏を金髪美人のボべスコがエレガントにヴァイオリンを奏で、さらにこのCDには負けず劣らずの佳曲第23番も併録されているのが嬉しい。
それにしても、今回取り上げた二枚のディスクはもう半世紀以上前の録音である。そろそろ最新の録音で聴いてみたい気もするが、新録音は一向に現れそうにない。
まあ、レトロな雰囲気がこの曲に合っているような気がしないでもないが。