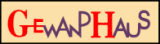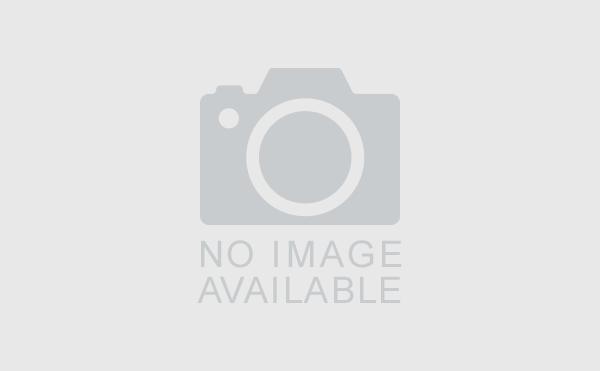シベリウス:交響曲第三番ハ長調Op.52
あと千回のクラシック音楽リスニング(40)
シベリウス:交響曲第三番ハ長調Op.52〜
~ 真夏のひと日のための一服の清涼剤たりえるシンフォニー ~
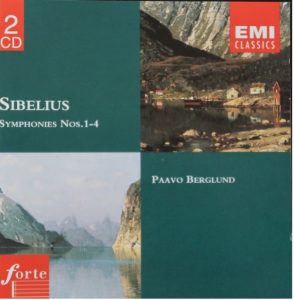
梅雨明けからの猛暑は当たり前だが、今年の暑さは異常である。北海道でも40℃なんて、ありえない暑さである。
さて、この暑さの中で何を聴こう。涼しさを喚び起こすような音楽となるとまず第一に挙げるべきはシベリウスではないだろうか。
となると、例えば第四番とか第七番、しかしこの2曲、私にとってはわかったような、わかってないような不思議な存在なのである。とくに前者は氷の結晶を観察しているようで、どの部分も美しい音のシークエンスを聴いているみたいなのだが、私の脳は何ら感情的反応を起こさない。傑作だと予測し、沢山の回数、聴くのを重ねて、理解できたような気がしているのだが、自分とは別世界の音楽みたいな気がするのである。実際のコンサートで聴けば一皮むけた聴き方が出来るかもしれないのだが。
一方、第七番はコンサートで、しかも渡辺暁雄&京都市響、エフゲニー・ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル、そしてパーヴォ・ベルグルンド&ヨーロッパ室内管と、この作品のスぺシャリトみたいな指揮で聴いているのに、感動を覚えたことがない。
そういう訳で、私がこの季節に取り出すことが多いのは第三番ハ長調である。
これも不思議な作品である。前期と後期の橋渡しのような作品なのであるが、まずこの第三番礼賛みたいな文章に出逢ったことがない。
そして、このハ長調というのが気になる。私はこのハ長調と言う調性が苦手である。モーツアルトの最後のシンフォニー、ベートーヴェンの第一番、シューマンの第二番、ハイドン「皇帝」、モーツアルとのピアノ協奏曲第25番などなど。何というか音楽に深さを刻み込むのが難しい調性みたいな先入観があって、ハ長調で愛聴曲というとシューベルトの「グレイト」くらいしか頭に浮かばなかった。
ただシューマンの第二は今ではシューマンの交響曲で一番聴く回数が多い不思議な作品である。シューマンの第二番はかってはオットー・クレンペラーとヴォルフガング・サヴァリッシュによる全集が二組あったのにも関わらず、なかなか食指が動かなかった。それは一つには名曲とは思っていなかったこと、それにハ長調という調性が加わったためであると自己分析している。ところがある時、第三楽章の祈りにも似た深いアダージョを聴くに及んで全曲を聴き始め、結果として現在最もよく聴くシューマンの作品となっている。先入観はいけない。
このシベリウスの第三番も似たような経緯で、真剣に聴こうとはしなかった。かつて購入したジョン・バルビローリ指揮ハレ管のLPは第六番と組み合わせだったが第六番ばかり聴いていて、第三番のサイドをかけることはなかったのである。
ところがである、ある時期からこの第三番は愛聴曲に変身となった。
きっかけはエディンバラ音楽祭での経験である。
1998年にエディンバラで国際植物病理学会が開催され、開会式は有名なアッシャー・ホール、そこでロイヤル・ファミリーからご挨拶を賜ると言う光栄に浴したが、その日程が音楽祭の真只中という、更なる幸運が待っていた。ベルナルト・ハイティンク指揮によるヴェルディ「ドン・カルロ」、アンドラーシュ・シフによるバッハの平均律、ウィーン六重奏団によるモーツアルトの弦楽五重奏曲などなど。シフのリサイタルでは隣にハイティンクが座り、会話を試みた。「あなたがベルリン・フィルを振ったマーラーの第二と第三のLDは素晴らしい」などと持ち上げた。実際はその2枚以外はこの指揮者による愛聴盤はなく、何というか、大家風と褒める評論家も結構いたが、私は芸術とは「突き詰める」ものだと信じているので、そこが欠如しているように感じるのである。後に東京で彼がロンドン交響楽団を振ってブルックナーの第九交響曲を演奏した折もそういう印象はぬぐえなかった。さて、エディンバラ音楽祭に戻って、その年の目玉はベルグルンド指揮ヨーロッパ室内管のシベリウスの交響曲サイクル(チクルス)だった。私は幸運にもそのサイクルの全演奏会のチケットを手に入れることができた。そして、全く期待していなかったこの第三番にやられてしまったのである。
楚々とした「春がやってきた」みたいな第一楽章の始まりからフィナーレのコーダまで、引き込まれ感動した。
とくに第二楽章の愛すべき旋律の数々、静かな悲しみを湛えたような美しい旋律の連続。消えてほしくないと思うほど、その旋律は魅力的であった。
舞台の指揮台上ではベルグルンドが例の左ききの棒さばきで淡々と振っていた。その姿を眺めてあるイメージがその時浮かび上がった。それは墓地をベルングルドが袈裟を着て、徘徊している様であった。そう、美しい旋律が流れているにもかかわらず、「寂寥」の極みみたいなものを私は感じていたのである。
フィナーレで長調に戻って、ようやく北欧の野辺を、美しい小さな花を愛でながら散策しているような喜びを感じ始めていた。
そのサイクルの中で、ひときわ感動したこの交響曲、特に第二楽章はエディバラから移動したベルギーまで耳にこびりつき、以来特別な愛聴曲となった。
ベルグルンドはボーンマス響、ヘルシンキ・フィル、そしてヨーロッパ室内管(映像もあり)と3度も全集を録音している。どれも素晴らしいが、彼の「進化」は「純化」に向かっていた。最後のヨーロッパ室内管は実際にコンサートで聴いて感動したにも拘わらず、録音では石清水のようである。実際、私はそのサイクルを聴く前は、室内オーケストラで例えば第二番のフィナーレのコーダなど迫力が足りるのかなと心配していた。しかし、物理的には大オーケストラに及ばないかもしれないが、十二分に満足した。一方で、彼がベルリン・フィルを振った全集というものが存在したら、そんな「夢」も湧いて来る。カラヤンとはどんな差が生じるのだろうか、など。
現存する3組の全集であるが、CDで聴く場合はヘルシンキ・フィル盤が好ましい。そして、この第三番を聴く場合、通常よりややヴォリュームを上げて聴く、何せ「純粋で楚々とした雰囲気の交響曲」なので。
ベルグルンドは実力派指揮者の典型で、スター指揮者にはならなかった。
しかし、その実力は誰もが認めるところであり、ベルリン・フィルとのライブ録音盤もある。特にネーメ・ヤルヴィはベルグルンドの信奉者であり、彼にあやかって息子にパーヴォと名付けたくらいである。
真夏の宵、ホップの効いた苦み系の冷えたビールを吞みながら、この第三交響曲を楽しみたい。
(付録)「エディンバラの思い出」
イギリスに最初を訪れたのは1993年である。ケンブリッジで開かれたある国際ワークショップに参加するためだった。その前に国際機関に勤めていた時の上司が、国際植物病理学会のある委員会の長に選ばれたので、私にもぜひ参加しろという命が下ったのである。当時、海外出張はまだ難しい時代で、国際学会の参加は認めるが旅費は出ない、それで私はフィリピンで格安チケットを購入し、南回りでイギリスに向かった。マレーシア空港では8時間の待ち合わせ、空港はまだ出来立てで、巨大なサーカス小屋のようであった。さらに、クアラルンプール、ドバイなど何回も着陸する便で、長時間にわたるフライトであったが、その度に食事と酒類が供されるので喜んだ記憶が残っている。
初めての英国は印象深いものがあった。夕刻になると気温が一挙に下がり始め、ビールは冷やして飲まないのは当然というのを理解した。いや、冷やすとアロマが消えるという説もあった。
本屋やレコード店では欲しいものがあり過ぎて困った。しかも価格が安く、ペンギンCDガイドとバーンスタインのバイオグラフィー(H=バートン)を購入した。
映像系ではクラシックのビデオ・テープが安価で驚いたが、残念ながらPAL方式なので購入を諦めざるを得なかった。スコアーも安かったので、ブラームスの全集を買った。
次が上記したように、1998年、エディンバラでの国際植物病理学会参加である。
飛行機は嫌いなので、ロンドンからエディンバラまで鉄道で移動した。これはよかった。英国特有のなだらかな丘が美しく、海岸の景色も素晴らしかった。キオスクでビールを買って、日本風に列車の旅を楽しんだ。
正確にはエディンバラはスコットランの首都で、お城やスコッチ・ウイスキーで有名であるが、他にもバーバリ本店があり、オーディオではLINNもタンノイもスコッチなのである。かつてのテニスの四天王の一人アンディ・マレーもスコッチである。基本英国とスコットランドは歴史的経緯から仲が悪い。英国はマレーがウィンブルドンで優勝したら、「英国のマレー」と英国を強調するあざとさもある。
エディンバラの名物料理はハギスと言う牛の胃袋料理で美味しくない。「英国は美味しくない」は常識で、リンボー(林望)先生の「イギリスはおいしい」はパロディーである。イタリアン、中華、どれも不思議なほど味が落ちる(最近は大陸からイギリスへ料理人が流入し、料理が美味しくなったという話も聞いた)。なので、私はムール貝料理の店を見つけて、そこに通った。
さらにケチ。ケチをDutch accountというが、本来British accountと訂正すべきであろう。ワークショップでシェリー酒パーティーに招待されたので、出かけたのだがシェリー酒は一杯だけ、つまみはポテトチップスが小皿に載せてあるだけだった。スポンサーは農薬会社だったが、業界の招待でこんなケチなパーティーは世界広しといえども英国以外にはないものと思われる。これは一つの例である。
悪口が並んだが、英国人はアメリカ人を見下すような良識があるのも確かである。また、余裕と言うか、遊びがある。スリランカを訪れた折、カウンターパートの園芸研究所の病理部長は英国ロンドン大学で学位を取った男で、英国を知り抜いていたが、呑みながら話をしている時、「英国人は大人だね」で一致した。
エディンバラでの国際学会では参加者にスコッチ・ウイスキーのミニボトルが配られたが、ウイスキー博物館でそのブランドの多さに圧倒された。カウントレスの世界であろう。いつか宮﨑空港で宮崎県の焼酎展が開催されていたが、その蔵元の多さに驚いた。「霧島」はその代表にすぎない。だが、スコッチの場合、これはグローバル・レベルである。あんなに「味」にうるさくない英国人がウイスキーではアロマはじめ質にこだわるのか、これも不思議である。
また英国に行きたいと言うほど魅力は感じないが、アイラ島に行って、島の牡蠣を肴に荒々しいシングル・モルトを堪能したいという夢は持っている。