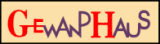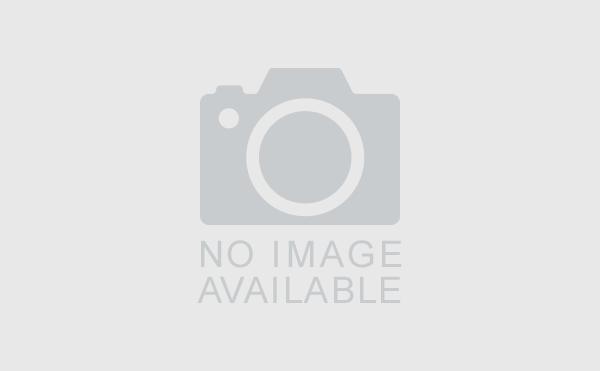シベリウス:交響曲第二番ニ長調OP.43
あと千回のクラシック音楽リスニング(41)
シベリウス:交響曲第二番ニ長調OP.43
~真夏のお昼のための「ウナギのかば焼き」的シベリウス~
レナード・バーンスタイン指揮ウイーン・フィルハーモニー管弦楽団
DG 417 772-2(輸入盤)
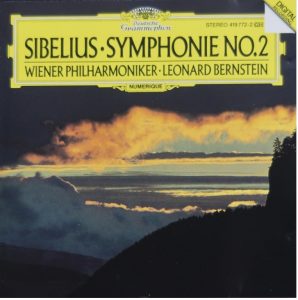
いやあ、まだまだ猛暑の毎日である、今年の夏は。
前回は「一服の清涼剤」としてのシベリウス交響曲第三番を採り上げたのであるが、今回は真逆のシベリウスである。レナード・バーンスタイン指揮ウィーン・フィルによる交響曲第二番、かば焼きのようなコテコテの脂ぎったパフォーマンス。そもそも暖色系のウィーン・フィルを振ってシベリウスなんて、という先入観があった。
濃い色彩、遅く粘ったテンポ。これはシベリウスではないと言う人もいようし、拒絶したり、嫌う人もいるに違いない。私も「シベリウスは余計なことをしてはならない。強い個性を出したり、余計な色をつけるとシベリウスの音楽は死んでしまう」と宣う有名な評論家のご意見をごもっともだと納得し、バーンスタイン指揮ウイーン・フィルハーモニー管弦によるシベリウス交響曲第二番は購入したものの、聴こうとしなかった時期もあった。
ところが数年前のある日、楽友にして呑み友Tさんが同じコンビのシベリウスの第一番の方を持参して飲みにやってきた。濃く、更にゆったりしたテンポなのだが、何故かとても魅かれる演奏だった。彼はニューヨークに長期出張中、ウィーン・フィルのニューヨーク公演でこの交響曲を聴き、感銘を受けたらしい。場所はカーネギー・ホールで、第三楽章スケルツォでのバーンスタインの指揮振りはまるで阿波踊りだったそうである。
私はこのCDをしばらく借りて、繰り返し聴いた。やはり素晴らしい演奏だと感じ入った。この第一番の録音は1990年2月、Tさんがカーネギー・ホールで聴いたのもほぼ同じ頃だったようだ。
それで、私が持っていた第二交響曲の方は1986年10月、ウィーンの楽友協会第ホールでのライブ録音である。4年ほどの時間の差はあるものの、基本は変わらずで、第二番は50分を超える大演奏である。因みに標準的なパーヴォ・ベルグルンド&ヘルシンキ・フィル盤は35分で終わってしまう。
これら2枚のバーンスタイン&ウィーン・フィルによるシベリウスのCDを聴きまくっての結果はテンポが遅くても、結果として造形がスケール大であっても、音色が温かくてもシベリウスの音楽は魅力的であり、最初持っていた違和感もいつしか消えてしまい、ユニークな名演という結論に達したのである。酒好き人間の私は思わず、「いい酒は冷やでも温めても美味い」という言葉を思い出す。
振り返ってみると、シベリウスの交響曲は学生時代から結構聴いていた。ステレオ盤はなかなか買えなくて、最初はロンドン(英DECCA)のMRシリーズというモノーラルの廉価版でのアンソニー・コリンズ指揮ロンドン交響楽団のLPで聴きまくった。その後、ステレオ盤ではピエール・モントゥー指揮ロンドン交響楽団のLPをよく聴いた。世評は高いが愛聴盤とはならず、CD時代となってコリン・デイヴィス指揮ボストン響とベルグルンド指揮ヘルシンキ・フィルによる全集を揃えてようやく落ち着いた。しかし、単発のものとして発売されたCDも何枚か加わった。
それらの中で異色の一枚がある。アレクサンダー・ギブソン指揮ロイヤル・スコティッシュ・ナショナル管弦楽団によるChandos盤(第二及び第五交響曲)である。滞米時、これはギブソンがどこかのオケを指揮してのシベリウス交響曲の第二番のラジオ放送で、それを研究用温室で学生がボロのラジオで聞いていた。すると、ブラスと打楽器がやたらと飛び出すバランスで、えらく迫力がある演奏に聞えたので、ギブソンという指揮者に興味を覚えたためである。
かつての昔、「レコード芸術」の別冊で「私の愛聴盤10選」みたいな本が刊行されて、当時私の敬愛する評論家・福永陽一郎氏がバーンスタイン&ニューヨーク・フィルによるシベリウスの第二番を採り上げておられ、フィナーレでの盛り上がりを「台風が近づいて来る時の興奮」に例えてあって、なるほどと納得したことを思い出す。
そうシベリウスの第二交響曲の魅力はフィナーレの盛り上がりに違いない。そのフィナーレの異常な盛り上がりで、どんな演奏でも元が取れるようなつくりになっている。
シベリウスのバイオグラフィーを読んでみると、時代的な背景があって、初演でも大好評を博したようだ。 交響詩「フィンランディア」にしても、この交響曲のフィナーレにしてもフィンランド国民の怒りや勇気を代弁したような表現となっている。そして、私はこの最後の盛り上げ、執拗なまでのリピート、どうもブルックナーの第九の第一楽章の終結部との相似性を感じていたのである。
実際、シベリウスはウィーンに留学しており、その時、彼が弟子入りを望んだのは何とブラームスであった。しかし、ブラームスは弟子をとらない、次にブルックナーを望んだ。しかし、ブラームスより高齢のブルックナーはもう引退宣言をしていた。結局、シベリウスはカール・ゴルトマルクに師事することになったが、ブルックナーの最後の交響曲を聴いた可能性はある。
驚くことに、シベリウスはウィーン・フィルのヴァイオリン・セクションのオーディションを受けている。しかし極端なあがり症の彼は合格しなかった。それでよかったのだ、もし合格していたら、大作曲家シベリウスは誕生しなかったかもしれないのである。そう言えば、フリッツ・クライスラーもウィーン・フィルのコンサートマスターのオーディションで落ちてしまったが、彼も採用されていれば、大ヴァイオリニスト・クライスラーは誕生しなかったに違いない。
もう一つ、シベリウスとブルックナーの相似性の話。ある時、ベルギーのゲントからアムステルダムへ、友人マーセルの運転で向かっていた折、カーステレオのスイッチを入れた時、どこかで聞いたことのある交響曲が大音量で鳴り始めた。マーセルは結構な音楽通で、数百枚のCDのコレクションがあり、B&WやNAIMを中心とする英国製オーディオのラインアップでクラシック音楽や民族音楽を聴いている男である。そして、彼はその交響曲のフィナーレ付近で、「これはブルックナーだな」と結論づけた。そしで、曲が終わり、アナウンサーが「只今の曲はシベリウスの交響曲第二番でした」と言ったので、二人で大笑いをした記憶がある。交響曲の一部を切り取って聴いてみると、結構当てるのは難しいものである。とくに、モーツアルトの後期の作品の緩徐楽章やブルックナーの作品のスケルツォなど即答は難しい。しかし、シベリウスの第二においてをや、である。
ところで、私にとって実際のコンサートでのシベリウスの第二交響曲初体験は何とジョージ・セル指揮クリーブランド管というゴージャスなものであった。1970年大阪万博の時で、私はこのコンサートのために夜行列車に乗って九州から大阪に出向いたのである。しかし、このシベリウスの第二にも、さらにモーツァルトの40番にも感動を覚えなかった。最初のカール・マリア・フォン・ウェーバーの「オイリアンテ」序曲での滑るような木管の流れには驚いた記憶があるが。肝心のモーツアルトにもシベリウスの名曲に感動できないなんて、である。
似たような経験はシカゴ響の定期のオープニングでのマーラー第八交響曲、クロージングの第九交響曲でのゲオルク・ショルティでも。どうも私は「管理型」とか「切り込み型」指揮者との相性がよくないようだ。
セルはザルツブルグ音楽祭におけるウイーン・フィルとのリハーサルで開口一番、「第一ホルン、君の音はだれている。直したまえ」と宣うたそうである。いや、その鄙びたホルンの音こそがウイーン・フィルなのであって、融通無碍など無縁のセル、私は嫌いである。ショルティも同様、「出をきっちりと合わせろ、みっともない」と喚き、コンマスのボスコフスキーをして「ショルティの首を絞めてやりたい」と言わしめた。そう、きっちり合わないのがウイーン・フィルの良さなのである。双方ともハンガリーのユダヤ系指揮者で、元ピアニストである。縦の線を揃えねばという基本的なアプローチがあるのだろう。
さて、今回のこのコラムの記事のため、久しぶりにシベリウスの伝記を読破した。
私はシベリウスはフィンランド国家のサポートを受けた国民的作曲家で、裕福な、作曲に専念できる環境で生涯を全うしたのだと思い込んでいた。ところが、実際は真逆に近い生活を送っていたらしい。
ヘルシンキでの遊興と浪費、シベリウスには経済観念というものがなかったようだ。
画家アクセリ・ガッレン=カッレラによる有名な「シンポジウム」という絵は当時のシベリウスのと指揮者カヤヌスとのレストラン「カンッピ」での交友の様子を描いたものである。シベリウスとカヤヌスは出来上がっていて視線が定まっていない。何というかカヤヌスにしてもシベリウスにしても怖い顔である。テーブルの上には高級ラム酒か、強い酒の酒瓶が林立しているが、一説によればシベリウスのお気に入りはシャンパンだったらしい。散財するはずだ。
この当時の酒と遊興に溺れたシベリウスは妻アイノが待つ家には帰らず、経済的にも困窮を招いてしまった。
「シベリウスは自然に囲まれたアイノラ荘へ移って愛妻アイノとフィンランド政府支給の年金のサポートで、独自のユニークな交響曲を創作した国民的作曲家」という私の先入観はもろくも崩れ去ってしまった。
愛妻家シベリウスというイメージも後年はともかく若い頃は遊興のための借金、また借金という借金の山でアイノは糟糠の妻だった。良家の出で、その美貌にシベリウスがひと目惚れしたアイノ、裕福な家庭環境で育ったにもかかわらず、彼女は夫の浪費にも耐えて、生涯を通じて作曲家シベリウスを支えた。アイノの内助の功は感動的である。
その生き様を眺めて、私はバーンスタインの妻フェリシアの生き様を思い出した。彼女も良家の出の才色兼備の女性だった。バーンスタインは音楽的な面では天才そのものであったが、ホモというよりバイセクシャル、さらに若い知的男性との駆け落ちまでやらかす破滅型人生。ストレスはいかばかりであっただろう。アルコールは分からないが、ヘビイ・スモーカーだった。そして、ついに肺ガンで亡くなった。1978年、56歳の生涯であった。私の滞米生活は1980-1981年だったが、バーンスタインはTVで頻繁にお目にかかれるものと思っていたら、アーロン・コープランドの80歳誕生日祝賀番組でのスピーチくらいしか現れなかった。お腹がプックリ膨れて、いかにも不健康そうな姿であった。フェリシアを亡くし、ショックと後悔の時期であったのだろう。そもそもその時期はサバティカル・イヤーだったようだ。
私はバーンスタインの芸風は4段階に分けられると考える。ニューヨーク・フィル以前、ニューヨーク・フィルの音楽監督時代、ヨーロッパ進出時代、そして晩年の巨匠的指揮の時代。
今回採り上げたシベリウスの第二交響曲はその最後の巨匠的に、どれもテンポを落とし、スケール雄大な演奏が特徴の時代に録音された。その時代、チャイコフスキーの「悲愴」に至ってはほぼ1時間の大演奏である。
バーンスタインの、この段々と暗い情念が漂い出すような、線の太いシベリウスはやはり異端的な演奏に違いない。バターをたっぷりと使ったソース、そんな料理に仕立て上げているようなシベリウス。それ以前にバーンスタインが何故全集と選集を録音したのかという彼の感性も興味深い。何せバーンスタインはウクライナからのユダヤ系移民なので、地理的にはともかく、民族的な同質性はないはずなので。しかも、シベリウスの後期の作品は内面を見つめたような、繊細さを特徴とする。
オスモ・ヴァンスカはフィンランド人と日本人は共通の感性を持っているとインタービューで発言しているが、フィンランド人はアジア系の血も入っているので、表面的なお世辞ではないのかもしれない。共通のキーワードは“メランコリー”とも言っている。しかし、バーンスタインのこの演奏では「メランコリー」を通り越して、「暗い情念」のように聞こえる。ずっと夜が続いて、明るい朝はやって来そうにもないような。
バーンスタインのこの不思議な嗜好とは正反対なのがラテン系の音楽家たちであろう。シベリウスの交響曲はやはりラテン系の民族の感性には合わないらしく、カルロ・マリア・ジュリーニ、クラウディオ・アバド、リッカルド・ムーティ、リッカルド・シャイーなどイタリアの指揮者のレパートリーには入っていない。シャルル・ミュンシュ、ポール・パレ―、アンドレ・クリュイタンス、ジャン・マルティノンなどフランス系の指揮者も同様である。
近年、パーヴォ・ヤルヴィやクラウス・マケラがパリ管でシベリウスを採り上げている現象はとても興味深い。トライアルで終わるのか、浸透し始めるのか。これからの展開が楽しみである。
一体、作曲者がこのバーンスタイン指揮ウィーン・フィルによる第二交響曲を聴いたら、どういう反応を示しただろうか。作曲者はユージン・オーマンディの演奏にいたく感じ入って、賞賛していたという記録が残っている。しかし、オーマンディは第三と第六番は理解できないと告白していたそうだ。実際、彼の選集にはこれら2作品は含まれていない。シベリウスは豪華なフィラデルフィア・サウンドに酔いしれたのかもしれない。
作曲者に考えが及びもしない想像もしない境地へと連れて行ってくれる演奏、それこそが作曲者を喜ばせる演奏と言うことになるのだろうか。
想像はエスカレートして行くのだが、シベリウスはレニー(レナード・バーンスタイン)のこの演奏を聴いて、狂喜したかもしれない。若き日の苦々しいウィーンの日を思い出しながらも。