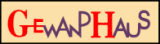ブーレーズ、異色のベートーヴェン
今回の紹介盤はピエール・ブーレーズ(Pierre Boulez/1925~2016)、異色のベートーヴェンである。 「交響曲第5番ハ短調」、俗に日本では「運命」の副題で親しまれている最もポピュラーな交響曲だが「第3楽章」 […]
グールドによるシベリウス作品集、1976~1977
シベリウスはピアノ作品も数多く書いたが交響曲や管弦楽作品の陰に隠れた存在だった。 斬新的なピアニストのひとりグレン・グールド(Glenn Gould/1932~1982)は家系も北欧の血をひきシベリウス作品を好み、今回紹 […]
バリリ弦楽四重奏団によるモーツァルト「弦楽四重奏曲第12番&第13番」、1955年モノラル録音
今年(2021年)矍鑠たる100歳を迎え祝福されたワルター・バリリ(Walter Barylli)が「ウィーン・フィル」コンサート・マスター時代に戦後結成したバリリ弦楽四重奏団も今や伝説の四重奏団となった。 このバリリ四 […]
ヘブラーによるモーツァルト「ピアノ協奏曲第19番・第26番 ”戴冠式”」、1961
今回の紹介するイングリッド・ヘブラーのモーツァルト「ピアノ協奏曲第19番&第26番”戴冠式”」(コリン・デイヴィス指揮ロンドン交響楽団)の録音は後のピアノ協奏曲全集録音(1964年~1973年)に先立つ1961年ステレオ […]
ヴセヴォロド・レジュネフのチェロ・リサイタル、オーディオ・ラボ制作LP
今回の紹介LPも懐かしい1枚である。 チェロのヴセヴォロド・レジュネフ(Vsevolod Lezhnev)は1931年モスクワ出身、1960年代末には活動拠点をアメリカに移しピッツバーグ交響楽団の副首席奏者も務めた。 紹 […]
「コルトー、ティボー、カザルス」トリオの歴史的名盤、大公トリオ1928
アルフレッド・コルトー(Alfred Cortot(Pf)/1877~1962)、ジャック・ティボー(Jacques Thiboud(Vn)/1880~1953)、パブロ・カザルス(Pablo Casals(Vc)/18 […]
フランス実力派ピアニスト のマリレーヌ・ドッス
マリレーヌ・ドッス(Marylène Dosse、写真1)も今年(2021年)81歳を迎えるアメリカを拠点に活動するフランス出身実力派ピアニストのひとりである。 近代フランス作品を得意とし米VOXにサン=サンースのピアノ […]
ウィーン・フィル室内アンサンブルによるベートーヴェン「七重奏曲」、1975
若きベートーヴェンは当時ウィーンのサロンなどで流行していたディヴェルティメント風の弦楽器のほか管楽器も加えた6楽章構成の「七重奏曲」を書いた。 ベートーヴェン唯一の七重奏曲作品で初演時も大変好評だったと伝えられている。 […]
ズービン・メータ&ロス・フィルによるベートーヴェン交響曲第7番、1974
今年85歳を迎えたズービン・メータのベートーヴェン交響曲録音は意外に少ない。 今回スポットをあてる「第7番」はロスアンジェルス・フィルハーモニック音楽監督時代の1974年4月当時この楽団の録音会場の一つUCLAのロイス・ […]