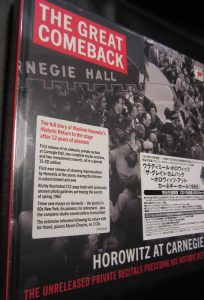ホロヴィッツ その7
そうは言っても、やはり当日の演奏は真の感動にはほど遠いものでした。 この一夜のピアノリサイタルは不振であったと言うよりもホロヴィッツの名誉を深く傷付けるものであったと言わざるを得ませんでした。
それでも、こう言えるのです。 演奏は残念であったけれども、ホロヴィッツの音を耳に出来た事実は万金に値すると。 こうした貴重な体験なしにはおよそホロヴィッツのシューマンの演奏について触れようなどと言う気にはならなかったと本音を申し上げておきます。
シューマンの演奏には必ずついて回る幻想性を蠱惑的に弾かなくてはならない音色の魔術が必要なのです。 それを両の耳で捉えるのは大変な事です。 やはり、いかなる響きを持っているか実際に聞くのが一番の近道だと言えますし、そうしないとなかなか正鵠を射ることが出来ないのです。
シフラの章で述べましたが既にこの世の人ではないピアニストの演奏に触れなければ要として本質にたどり着けないなどと言う事は言ってよい事なのか否かの問題になりますが、ここでは単に近道とだけ言っておきます。
アルフレート・ブレンデルが静寂に向かって収斂するクライスレリアーナを奏でるのと、壮年のホロヴィッツが奏でるのでは明らかに違うのは当然の事ですが、晩年のホロヴィッツの弾いたクライスレリアーナは微かに静寂の香りがしたように思われます。 壮年の時のクライスレリアーナは直線的に進むのですが、晩年のクライスレリアーナは徐々に減衰(音量や速度ではありません。 強いて言えば表現の強さでしょうか。)してゆくような気持ちの豊かさが(余裕と意訳しても構いませんが)あるのです。 音色の艶やかさは晩年の方が増している様に思われます。 恐らく多くの聴き手は壮年時代のホロヴィッツの演奏を好むでしょう。 ホロヴィッツらしいタッチの明快さと熱意ある疾走感。 曖昧なものを排除した幻想性。 シューマンの陰り。 これらは晩年のテクニックの衰えを指摘せざるを得ない演奏より、確かに掻き立てるような焦燥感にも似た情念を感じると思います。 二つの演奏を較べるつもりはありません。どちらにも他のピアニストが表現しないものがあるのです。
それは、ホロヴィッツの演奏スタイルと言うべきもので、小さなピースに分かれた小品で構成された楽曲のそれぞれに意味を与える演奏であると言う事です。 ホロヴィッツと同じ名前を持つもう一人の若い世代のロシアのピアニスト、アシュケナージのクライスレリアーナを聞くと小品の性格付はクライスレリアーナと言う全体に向かってなされているのが聴き取れます。 シューマンがクライスレリアーナに与えたのは急、緩、長調、短調の対比ではなくその順番での全体の流れが静寂に向かって収斂していくことにあるなら、ホロヴィッツはシューマンの分裂的な部分に演奏を持っていこうとしている、すなわち、小品の集まりのテイストに近つけるのです。 特に壮年の演奏は強烈な弾奏が小品同士、距離をおこうとするように表現されているのにも関わらず、全体にまとまろうとする道を突き進むのです。
いささか、ホロヴィッツの演奏の真似をしたように文章が超絶技巧的になってしまいましたが、小品の演奏を得意としたホロヴィッツが手慣れた調子でクライスレリアーナを8曲の小品の集合体として演奏しながらその厳しい演奏ゆえに一つのまとまりを見せると言えば分かりやすいかもしれません。
(つづく)